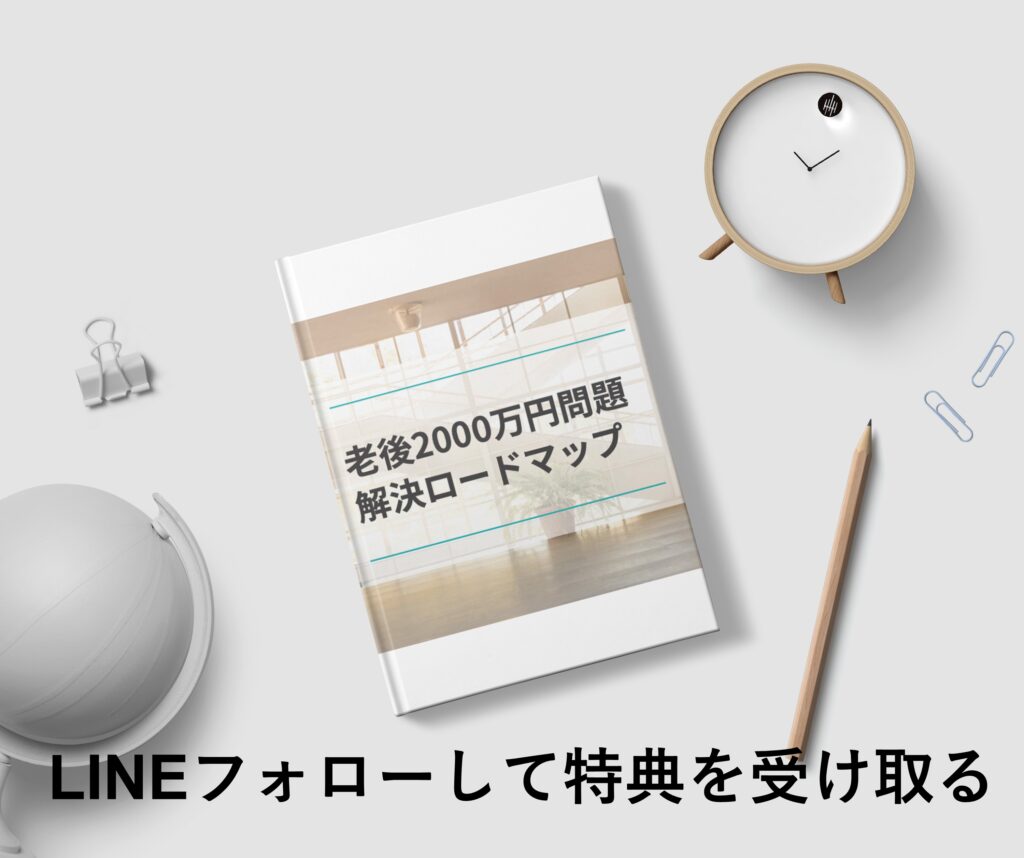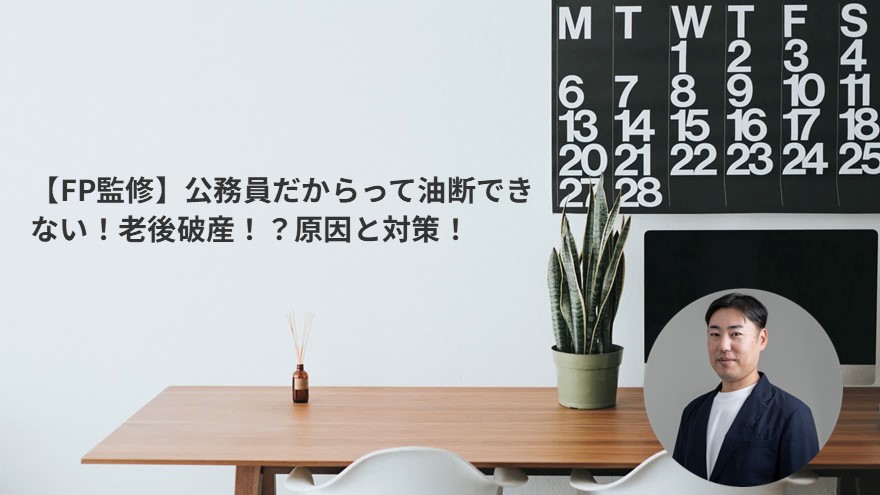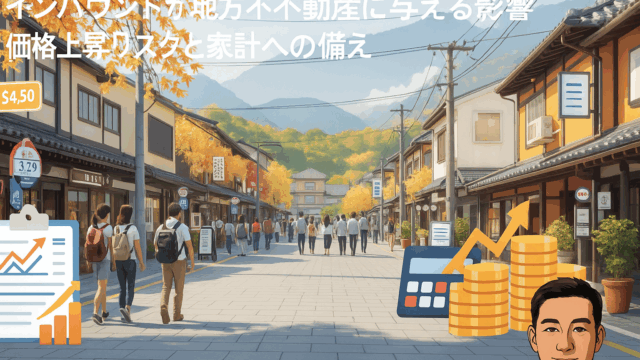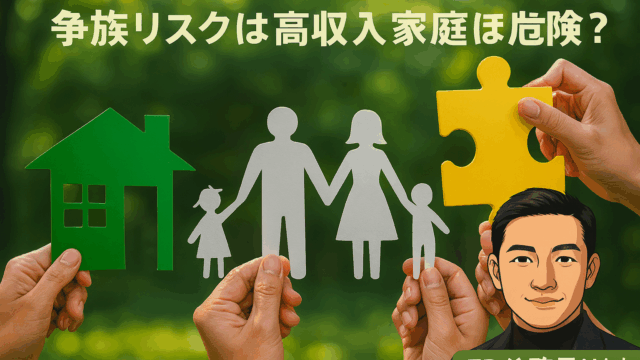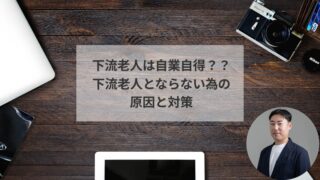老後破産とは、高齢者が年金や貯蓄だけでは生活費を賄えなくなり、経済的に困窮することを指します。ファイナンシャルプランナーや経済ジャーナリスト等が老後破産をタイトルに乗せ本を出版しています。
老後2000万円問題が一時期TVやネットのニュースで取りざたされていましたが、定年退職の時点で、2000万円もの金額を貯蓄できている方はいるでしょうか。
特に、一番安定していると思われている、公務員。
公務員だから安心だ、と油断していると最悪の場合、生活困窮者、老後破産の状態に陥ってしまいます。
退職金で、世界一周旅行や、高級車に乗ってみたい、住宅ローンの返済に充てて悠々自適な生活を送りたいそんな考えをお持ちのあなたにお伝えしたく、今回は、元銀行員であり、現役ファイナンシャルプランナーが、どのようにすれば、老後破産に陥らずに豊かな老後を暮らせるのかについてお話していきたいと思います。
元公務員のとある疑問
Aさんは2019年に60歳で定年退職をした元地方公務員の男性(65才)です。子ども達とは別居しており、専業主婦の奥さん(62才)と2人暮らしをしています。
子どもは2人で、2人とも高校大学と私立を卒業し、一般企業に就職しています。子育てにお金や時間がかかっていたので、老後は、それぞれの趣味や好きなことにお金や時間を使いたいと考えていました。
ところが、現役時代によく海外旅行に出かけたり、衣服にお金をかけたり、良い車に乗ったりと「周りの友達よりも少し良い生活をしたい」思いで生活してきたもので、おまけに、住宅ローンの返済や子育てでお金を使い、現役引退後に「こうしたい」と思うように生活できたのは、たったの3年間だけ。
安泰だと言われる公務員がこのようになってしまったのは一体なぜでしょうか。
老後破産、公務員でも老後資金2000万円が枯渇する2つの原因
地方公務員(以下公務員)には2000万円前後の退職金があります。
しかし、今後の支給額は減少していく見通しです。
公務員の年金支給額は、「3階建て制度から2階建て制度」になり、更に、今後、増税や経済状況の変化でインフレ率が上がっても年金支給額は上げないとされるマクロ経済スライドの導入により、財政破綻することなく年金を支給できるようにしていく流れになってきています。
また、2014年の厚生労働省の発表によると「30年後の年金支給額は、今より2割程低くしなければならない」との発表もあります。
毎月4万円超の赤字になる老後の収支
公務員の年金支給額が、2階建て制度に変わったので、一般の家庭と同等であると考えて記載していきます。
金融庁の第21回市場ワーキング・グループ(2019年6月)において厚生労働省が提出した資料を確認すると、2017年度の高齢夫婦無職世帯の毎月の平均支出額は26万3718円でした。
一方で年金受給額は19万1880円。その他の収入を合わせても20万9198円なので約5万5000円不足しています。要するに毎月の家計は赤字で、貯蓄などを切り崩して生活していることが分かります。
実はこれが2019年に世間を騒がせた「老後資金2000万円問題」の根拠となっています。同ワーキング・グループが公表した報告書『高齢社会における資産形成・管理』には、「夫婦で95歳まで生きたとすれば年金生活は30年。
したがって、年金だけでは足りない金額を補い続けるとすると、毎月の赤字5万5000円×12ヵ月×30年=約2000万円の貯蓄が必要である」といった内容が記されていたのです。
公務員には、特別に掛金を負担していく「年金払い退職給付」というものがありますが、もらえたとしても毎月1万円前後のものです。
ですので、平均値から算出してみると、例えば、1万円年金支給額が増えたとして、毎月の赤字4万5000円×12か月×30年=約16百万円が手許からでていくこととなり、ギリギリの生活が強いられます。
現時点での試算になるので、今後の人口減少、少子高齢化になっていく社会を考えていくと年金制度が良くなるとは決して考えにくいものです。
実際に年間1%ずつ減少し、支給開始年齢の引き上げも検討されています。
また、公務員は、60歳で定年退職し、65歳から年金受給する仕組み(1961年生まれ以降の方)になっているので、この5年間で大幅な赤字も予想されます。
上場企業等の大規模な会社であれば、子会社や関連会社への出向等で収入はダウンするものの定期的な収入でカバーしていくことができますが、公務員の場合はそうはいきません。
円の価値下落による、物価高
2012年のお亡くなりになられた安倍元総理の時代に遡りますが、アベノミクスにより、円の価値及び、物価上昇が始まったことも老後破産の原因の一つとして挙げられます。
そもそも、アベノミクスとは、安倍元総理が表明した「3本の矢」を柱とする経済政策のことです。最大目標を経済回復と位置づけ、①大胆な金融政策(デフレ脱却を目指し、2%のインフレ目標が達成できるまで無期限の量的緩和を行うこと)、②機動的な財政出動(東日本大震災からの復興、安全性向上や地域活性化、再生医療の実用化支援等に充てるため、大規模な予算編成を行うこと)、③民間投資を喚起する成長戦略(成長産業や雇用の創出を目指し、各種規制緩和を行い、投資を誘引すること)という3本の矢によって、日本経済を立て直そうという計画です。この計画に沿って政策が動いてきたため、インフレが今になり、顕著に表れてきています。今後も、量的緩和政策は続くので、物価高による収支の悪化は、進むでしょう。
どうすれば、老後破産せずに、悠々自適に暮らせるのか2つの対策
ここまで、公務員も老後破産の対象となりうることを記載してきましたが、年金の問題、物価高等老後破産のリスクもしくは、生活困窮者にならずに、対策をしていく必要があります。
もし、何もしなければ、退職金で、世界一周旅行や、高級車に乗ってみたい、住宅ローンの返済に充てて悠々自適な生活を送りたいそんな考えを持っていたとしても、収支を考えるとそんな余裕等ありません。
ですので、以下に2つの対策について示していきます。
NISA・iDeCo等での運用
NISAは、ご存知の方が多いかもしれませんので簡単にご説明致します。
NISAとは、少額投資非課税制度といい日本の個人投資家向けの税制優遇制度で一定額までの投資に対して売却益や配当金が非課税になる仕組みです。
NISAには、2種類の枠があります。
1積立投資枠
長期・分散投資向け
対象商品:金融庁が認めた投資信託やETFのみ
非課税期間:無期限
年間投資上限120万円
2成長投資枠
個別株や幅広い投資信託も対象
非課税期間:無期限
年間投資上限:240万円
NISAのメリット
売却益や配当金が非課税(通常は約20%の税金がかかる)
長期的な資産形成に有利
制度が恒久化され、非課税期間が無制限に(2024年から)
NISAについての説明は別ページで説明しますので、詳しくは、そちらをご参照下さい。
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことをいいます。自分で積み立てて運用し、60歳以降に受け取ることができる私的年金制度です。掛金の全額が所得控除の対象となり、税制優遇が受けられるのが大きな特徴です。公務員でもiDeCoの加入が認められています。
iDeCoの仕組み
毎月決まった額を拠出し、自分で運用商品を選ぶ(投資信託、定期預金、保険など)
60歳以降に一時金または年金として受け取る(運用成績によって受取額が変動)
iDeCoのメリット
1掛金が全額所得控除⇒所得税・住民税が軽減される
2運用益が非課税⇒NISAと同じく、通常約20%かかる税金がゼロ
3受取時にも税制優遇⇒一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除が適用
iDeCoのデメリット
60歳まで引き出せない(途中解約不可)
運用リスクがある(選ぶ商品によっては元本割れの可能性)
手数料がかかる(加入時、運用時、受取時に費用が発生)
ハイスピードの資産形成:不動産投資
NISA、iDeCoよりもハイスピードで資産形成できる方法として不動産投資が挙げられます。
不動産投資により取得した物件は、家賃収入が自身の所得となるため、個人年金保険の役割をはたしてくれます。
公務員の方であれば、ローンも通りやすいので、より区分所有マンションであればより多くまたは、マンション1棟等の物件を組むことができます。人口動態等をよく調べて、立地の選定を間違わなければ、家賃収入の増加を見込むことができます。
また、個人年金保険とは違い、家賃収入に加えて「不動産」という現物資産を保有できることもメリットです。
不動産を含む現物資産は、国の政策もあり、上昇を続ける見通しです。さらに、不動産に関しては、管理は不動産管理会社に任せることができるため、毎日の本業で忙しく、投資に時間を割くことが難しい高所得者が取り組みやすいのです。
プラスアルファでのお悩みとして、税金対策にもなります。不動産所得は、総合課税の一つに分類されるので、投資用のマンションを購入し、物件を賃貸した場合、給与所得等と合算されます。
ですので、減価償却費や固定資産税、修繕費(修繕は単なる支出ととらえるのか資本的支出になるのかで変わりますが)などで赤字計上することで、給与所得等と相殺することができます。
一方、株式や投資信託の配当金、分配金等は、分離課税となるので、相殺されません。また、相続の話になりますが、1棟マンションや戸建ての住宅の場合、建物の評価方法が、貸家建付地評価という算出方法になるので、現金で持っているよりも評価額を下げることができて、相続対策になります。
尚、売却時は、相続時と違い、収益還元法やDCF(ディスカウントキャッシュフロー)法等での評価がベースとなりますので、物件単体での賃料収入や立地、支出によって変わりますので、現在の日本の経済情勢を考えると上昇することが見込まれます。
ですので、売却時には、税金がかかる可能性があるので、よくご検討したうえでタイミング等を判断してください。
公務員は副業禁止ではないのか、という疑問があるかと思います。インターネットで調べていただくとわかるかかと思いますが、以下の条件を満たせば公務員であっても不動産投資をすることができます。
・不動産規模が5棟未満
・不動産規模が10室未満
・投資による収入が500万円未満
まとめ
ここまで、老後破産についてざっと書いてきましたが、公務員という職業であっても、決して老後が安泰といえる世の中ではなくなってしましました。
一方で必要な対策をきとんと立てれば老後破産をする心配もなく生活をすることができるようになります。
退職金で、世界一周旅行や、高級車に乗ってみたい、住宅ローンの返済に充てて悠々自適な生活を送りたいそんな考え実現させるためには、自分で必要な情報は取りに行き、行動を起こす、自分のことは、自分で守る、自分だけでなく大切な奥様や家族を守る心がけが必要です。
とはいうもののどうやって情報を得ればよいのか、どんな情報が必要なのかがわからないその為に行動が起こせない。
そんな場合は、信頼できるお金の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談してみてください。
また、このプログを読んでくださった皆さんへ、私のLINEを是非フォローしてくみてください。今なら、限定特典付きプラス、無料相談もできますので、是非是非LINEをフォローしてみてください。