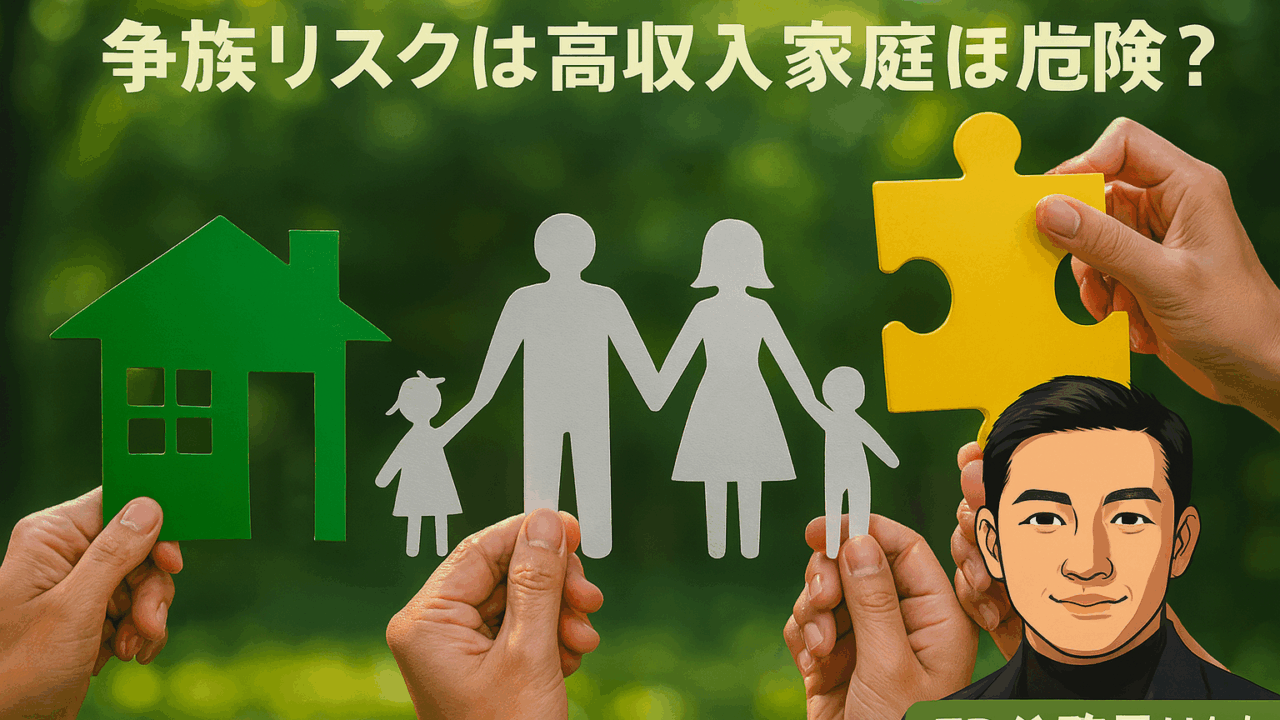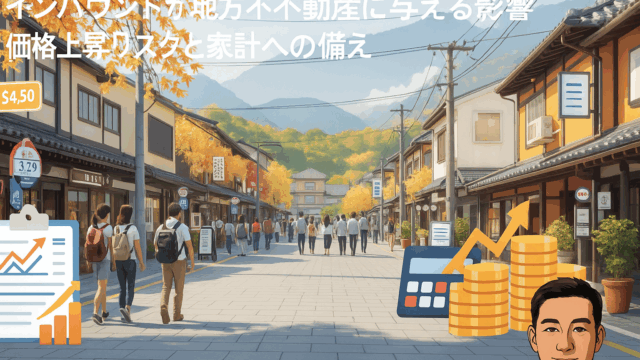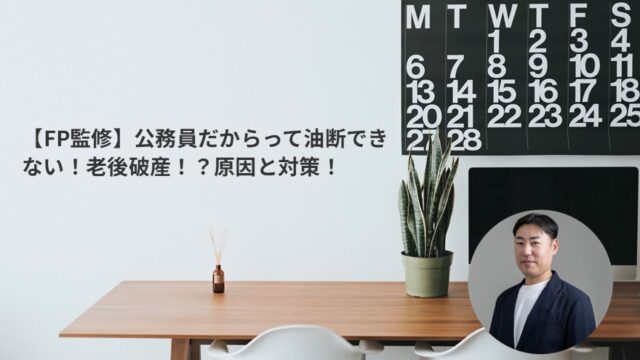相続のタイミングは、家族の絆を深めるチャンスである一方、時に“争族”と呼ばれる深刻なトラブルを引き起こすリスクも孕んでいます。特に高収入家庭においては、その資産規模の大きさがかえって家族間の対立を招きやすくなるという傾向があります。なかでも不動産は「分けにくい資産」として、遺産分割を巡る火種となることが少なくありません。
本記事では、相続対策として注目される「不動産投資」の活用法を中心に、“争族”を未然に防ぐための戦略を解説していきます。家族の未来を守るために、早めの準備が鍵となるでしょう。
相続でもめる家庭の共通点とは
相続でトラブルに発展する家庭には、いくつかの共通点があります。まず、遺言書や生前の対話が不十分なことが大きな原因です。特に高収入家庭では、資産が多岐にわたるため、誰に何を遺すかを明確にしておかなければ、相続人同士での認識にズレが生じやすくなります。
また、資産構成に不動産が占める割合が高いと、現金化しにくく分割もしづらいため、分配を巡って意見が対立するケースが多く見られます。国税庁の資料でも、相続税の課税対象となる財産のうち、不動産が占める割合は約40%を超えると言われており、その重要性は無視できません。
特に、日本の文化では「お金の話」を家族間で避けがちですが、それが原因で認識のズレや誤解を生むケースが後を絶ちません。さらに、「うちは仲が良いから大丈夫」という過信も危険です。相続が発生すると、普段は見えなかった金銭的な期待や感情が噴き出すこともあるのです。
実際、プレジデントオンラインで紹介された事例では、年収2,000万円の家庭で相続時に意見の対立が起き、結果的に絶縁状態にまで発展したケースが報告されています。このような問題は決して他人事ではなく、誰の身にも起こりうる「家族のリスク」として捉えるべきです。
なぜ不動産が争いの火種になるのか
相続財産の中でも特に「不動産」は、争族の火種となりやすい資産です。その主な理由は、現金のように簡単に分けることができない点にあります。
たとえば、ひとつの土地や建物を複数人で共有する形で相続すると、将来的な売却や活用の判断をめぐって意見が一致しないことが多く、結果的に対立が生まれてしまいます。
さらに、不動産には評価額と実際の市場価格との乖離があることも多く、相続人の間で「取り分が少ない」「不公平だ」といった不満を生み出す温床になります。
加えて、不動産が「争族の引き金」になる背景には、感情面の問題も存在します。たとえば、長男が親の介護を一手に担っていたにもかかわらず、相続時に不動産を均等に分けられてしまい、不満が爆発するというケースもあります。
情報誌でも、実家の処分や共有名義でのトラブル事例が多数紹介されています。被相続人にとっては思い出深い自宅であっても、残された家族にとっては「重荷」となることもあるのです。
不動産投資が有効な相続対策になる理由
争族のリスクを回避するためには、事前の相続対策が不可欠です。その中でも「不動産投資」は、節税効果と資産分割の柔軟性の面で優れた手段とされています。また、収益不動産を法人で購入しておけば、個人の課税対象から外れるうえに、所得分散や法人税率の活用によって資産全体の節税が可能になります。
こうした戦略的運用は、日本FP協会や大和証券の資料でも「次世代への資産承継の有効手段」として高く評価されています。
不動産投資には、物件の種類や立地、管理の方法などによってさまざまな選択肢があります。たとえば、築古の中古マンションを購入して安定収入を得ながら、将来的に相続対象として扱うことも可能です。市場価値と評価額の乖離を理解し、それを戦略的に活用することが、家族内トラブルを未然に防ぐ鍵となります。
法人化・信託で防ぐ争族トラブル
不動産を賃貸運用することで、相続時の評価額を抑えつつ、現金収入を得ることが可能になります。さらに、複数の物件に投資しておけば、相続時に物件ごとに分けることができるため、相続人間での不公平感を減らすことができます
不動産を活用した相続対策をさらに進める場合、「法人化」や「家族信託」といった仕組みを活用することで、より確実な対策が可能になります。
- 資産を会社名義にすることで、個人の相続対象から除外し、相続税の課税対象資産を圧縮できます。
- 法人で一元管理を行えば、物件の維持管理や賃貸運営の継続性を高めることができます。
- 資産の所有権と管理権を分離する仕組みです。
これにより、たとえば高齢の親が認知症になっても、あらかじめ指定された受託者が資産を適切に管理できる体制を整えることが可能です。
みずほ信託銀行の情報によれば、信託を活用することで相続時の混乱を大幅に軽減できるとのこと。
事業継承や介護期の資産管理にも柔軟に対応できます。
最近では、司法書士や税理士と連携した「信託組成コンサル」も普及し、複雑なスキームも手軽に導入可能に。
👉 正しい理解と実行こそが、家族の絆を守る最良の武器になります。
家族信託と法人化の具体的な活用例
東京都のAさん(60代)は、3人の子どもに不動産を円滑に継承するため、築30年の賃貸マンションを家族信託の枠組みで長男に管理を委託しました。本人が高齢化により意思判断が難しくなる前に、賃料収入の分配ルールを明確化しておいたことで、後の相続時に揉めることなく運用が継続できたと言います。信託契約には司法書士が関与し、信託財産の管理・処分について明確な指示が盛り込まれていたことが成功のカギとなりました。
福岡県のBさん(50代)は、アパート3棟を個人から法人に移管し、資産を法人名義で保有する形に切り替えました。これにより、自らが亡くなった後も子どもたちが法人を通じて賃貸経営を継続し、遺産分割で揉めることなくスムーズに資産承継できたそうです。法人を設立することで相続財産としての評価を圧縮し、相続税対策としても効果的だったといいます。

争族の発生率と統計的背景
日本FP協会の2022年調査によれば、相続経験者のうち「遺産分割を巡って揉めた」と答えた割合は約30%にのぼります。さらに、その中でも資産額が5,000万円を超える家庭においては、争いに発展した割合が4割を超えるというデータもあります。
また、信託銀行が行った別の調査では、相続人間の不満の大半は「取り分に納得できない」「相続の話をされなかった」といった感情的な要因に起因しており、法的に正しい手続きだけでは争いを防げない現実が浮き彫りになっています。
不動産投資で節税できる理由とは?
不動産投資が相続税対策として有効な理由は「評価額と時価のギャップ」にあります。相続税の計算に使われるのは実勢価格ではなく「路線価」や「固定資産税評価額」といった低めの評価基準です。さらに、賃貸中の物件には「貸家建付地」「貸家」(注)としての評価減が適用されるため、同じ価値の現金よりも大幅に評価額を抑えることができるのです。
(注)
貸家建付地とは、貸家の敷地の用に供されている宅地、例えば、その宅地を所有する方が建築したアパートやビルなどを他に貸し付けている場合の、その敷地である宅地をいいます。
貸家は、一戸建ての住宅を賃貸する形態を指します。所有者が家賃収入を得るために、第三者に貸し出す物件のことです。まとめ:今から備える「家族を守る相続準備」
相続対策は「まだ早い」と感じてしまいがちですが、問題が起こるのは準備を怠った家庭にこそ多いのが現実です。特に不動産を含む資産は、評価や分割の難しさがトラブルの火種となりやすく、感情面の摩擦も加わることで「争族」へと発展します。
不動産投資を活用した相続対策は、節税・分割・継続性の面で多くのメリットがあります。さらに、法人化や信託といった制度を取り入れることで、争いを未然に防ぎながら、家族の未来を安心して託せる環境が整います。
大切な家族に「資産」ではなく「負担」を残さないために。今日からできる一歩を、今こそ踏み出してみませんか?
📘 無料プレゼントのご案内
🎁この記事を読んで「自分もちゃんと備えなきゃ」と思ったあなたに、『資産形成スタートガイド(PDF)』を無料でプレゼント中です!
- 年金・退職金の見込み額が分かる
- NISA・iDeCoの活用方法がわかる
- 老後に必要な資金のシミュレーション付き
こちらから受け取り可能です👇 不安を「数字で見える化」して、安心な将来への第一歩を踏み出しましょう。