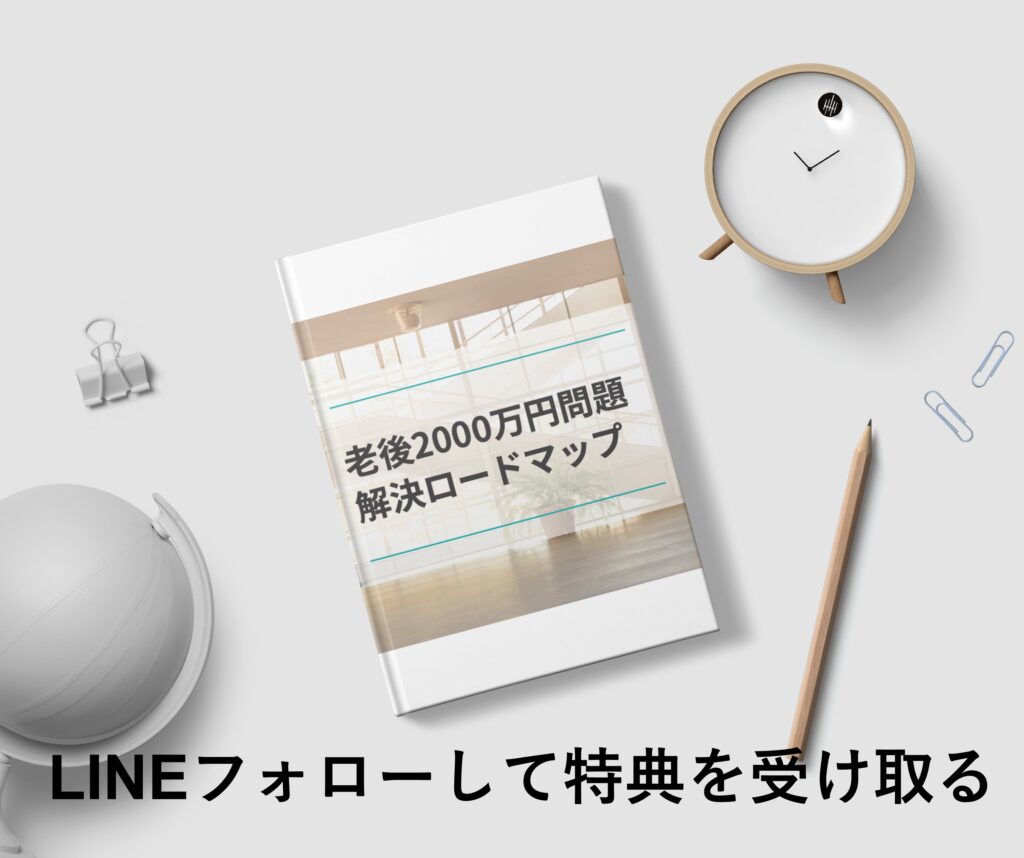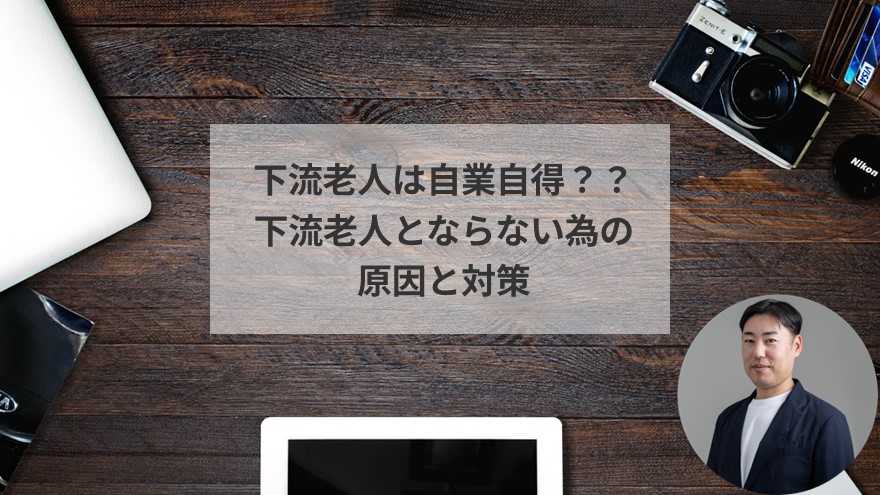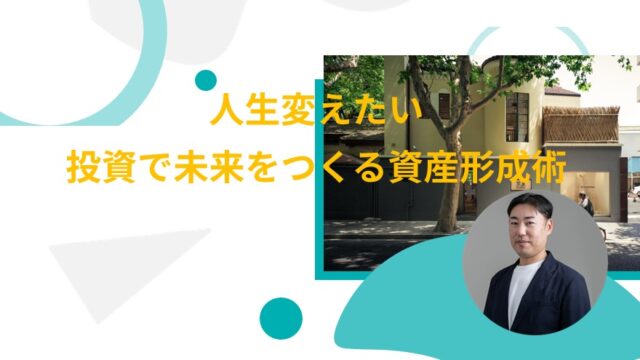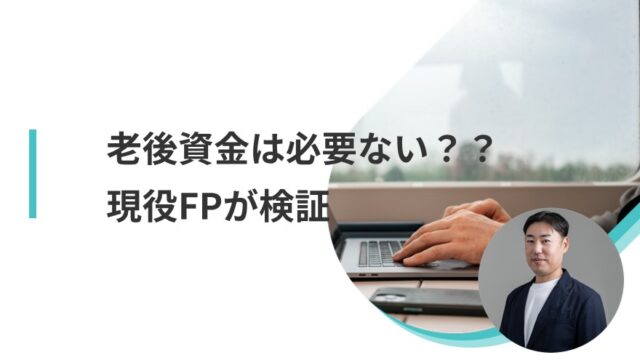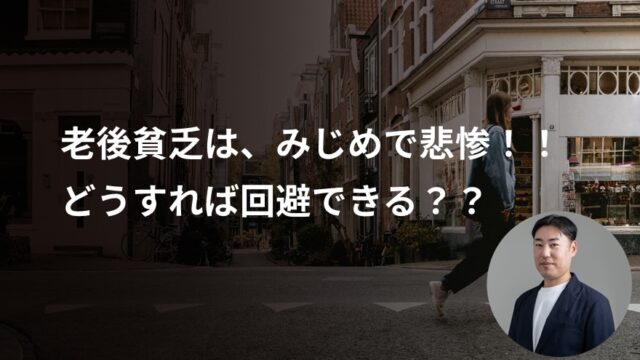昨今、下流老人や老後破産等、老後に対してネガティブな用語を耳することが増えました。老後資金2000万円問題等もニュースで騒がせたのを覚えていることでしょう。
団塊の世代が老後長生きし、平均寿命が80歳を裕に超え(男性81歳、女性87歳)ている中で、現役世代の負担が増えてきています。
現役世代が負担した分で現在のリタイアした方々の年金を賄っている一方で、現在の現役世代がリタイアした時のことを考えると年金が本当に受け取れるのか?等将来どうなっていくのか不安を覚えることもあるでしょう。
ネットに掲載されている記事の一部には、下流老人になるのは、自業自得だと書かれてるものもありますが、国が様々な政策を打ち出す中、何も対策を取らずに生活しているからそのように書かれるのも無理有りません。
現役世代で、一般的な企業にお勤めの方で、老後は年金や財形貯蓄をしているから安心だと油断しているととんでもない老後になってしまうケースも見受けられます。
今回の記事は、元銀行員であり、現役ファイナンシャルプランナーが、下流老人にならないためにどうしていくとよいのか、自業自得だと言われないためにどうすればよいのかを示し、将来への不安を払拭できるようにしていきます。
なぜ、下流老人となってしまうのか
「下流老人」という言葉は、経済的に困窮し、社会的にも孤立してしまう人を指す言葉です。
定年退職後に、退職金が少なく、年金の給付額も少ないため貯蓄額がほとんどない方が当てはまります。
なぜ下流老人となってしまうのでしょうか。
収入の低下と貧困
まず、年金収入の実質的な減少と受給年齢の引き上げ、物価の上昇が挙げられます。
物価の上昇については、アベノミクスにより、マネタリーベース、わかりやすく言うと、お金の総量が増加し、円の価値が下落することによって、物価の上昇が起こっています。それにより、生活費が予想以上に増えています。今後も更に物価の上昇は続くでしょう。
一方で、年金はというと、「物価スライド」から「マクロ経済スライド」というものに変わり、年金受給額が増える見込みは少なくなっています。
よって、思った以上に毎月の手許に残るお金が少ないまたは、マイナスの状態になってしまいます。
現役時の散財
現役時代に散財している方も下流老人予備軍と言えるでしょう。
自分へのご褒美とブランド物を購入したり、高級車に乗ったり海外旅行へ行ったり、高級店での飲食代金が多い方は注意が必要です。老後の貯蓄額を見越した、お金の使い方を考える必要があります。
厚生年金未加入
非正規雇用の増加により、厚生年金へ加入をせず、老後の年金収入が激減する恐れもあります。自営業者の方も要注意です。
予想外の出費
老後は、いくら現役時代に計画を立てていたとしても、思わぬ医療費や介護費が発生します。
マイホームをお持ちの方に関しては、思わぬ修繕費が発生するケースも出てきます。
こどもや孫への援助
こどもや孫への教育費の援助等も支出として考えておかなければなりません。
最近よく聞くケースとして自分のこどもが精神的な病気になり、働けない状態になったり、引きこもりになってしまったりして、こどもの生活費を賄う必要が出てくるケースもあります。
社会からの孤立
下流老人になるケースとして社会との孤立も挙げられます。
定年退職後、地域との接点を持たず、社会性がなくなり、孤独になり、地域からの援助を受けにくくなることもあります。
昨今は、未婚、離婚等により、孤立し、こどもからの援助を受けることができなくなるケースも耳にします。
生活水準を下げられない
現役時代の生活レベルを下げられず、どんどん貯蓄を切り崩していくケース等もあります。
生活水準を下げられない理由として、「定年まで頑張ったんだから老後は月に1回でも旅行に出かけたい」「いつかは乗ってみたい高級車」等現役世代に達成できなかったことを老後にやろうとしがちです。
充分な貯蓄等の資産をお持ちの方であれば、そういった生活でもやっていけるでしょう。
しかし、一般的なサラリーマンをしていた方々にとっては、そういう生活を何も対策せずに送るということは不可能に近いでしょう。
住宅ローンや借金の負担
定年後も住宅ローン等の借金を抱えていると、生活が苦しくなります。
お金に関する勉強不足や、情報収集不足:現役時代にお金の勉強や情報収集が不足して老後資金が蓄えられておらず、下流老人と化すケース。
家族構造の変化
かつては親と同居するのが一般的でしたが、現在は単身高齢者が増加してきています。
雇用の不安定化
終身雇用が崩れ、定年後に安定した収入を得にくくなっている傾向もでてきています。
下流老人とならないためにすべきこと3選
下流老人となるケースについて、挙げてきましたが、そうならないためにどのように対策をしていけば良いのでしょうか。
現状の収支状況を把握する
そもそもの話になりますが、現状の収支は把握できていますか。
リボ払いで何かを購入していたり、収入の範囲ギリギリでのローンを組んでいたり、ついつい散財してしまったりしていませんか。
決して、質素な生活を送りましょうということではありませんが、まずは、現在の収支状況を把握するところから始めましょう。見直せる部分は見直すようにご家族で話し合う等してみてください。
未来の出費を可能な限り書き出してみる
面倒かもしれませんが、起こり得る未来の出費をすべて書き出してみてください。
上記に挙げた下流老人となる原因を参考にしていただいても構いません。
現在は、学費がいくらかかるとか、介護費用がいくらかかるとか、インターネットで調べればすぐにでてきます。
ただ漠然と頭の中で思っているだけでは、抜け漏れが出てきますし、真剣に取り組む意識も芽生えてきません。
資産形成について学ぶ
近年TVやインターネット等で「貯蓄から投資へ」とよく言われていますが、何から手を付けて良いのかわからない方もいるかと思います。
誰でも簡単にできる積立投資から中級者・上級者に向けた投資方法についてご紹介したいと思います。
NISA・iDeCo高利回り商品での運用
NISAは、ご存知の方が多いかもしれませんので簡単にご説明致します。
NISAとは、少額投資非課税制度といい日本の個人投資家向けの税制優遇制度で一定額までの投資に対して売却益や配当金が非課税になる仕組みです。
NISAには、2種類の枠があります。
1積立投資枠
長期・分散投資向け
対象商品:金融庁が認めた投資信託やETFのみ
非課税期間:無期限
年間投資上限120万円
2成長投資枠
個別株や幅広い投資信託も対象
非課税期間:無期限
年間投資上限:240万円
NISAのメリット
売却益や配当金が非課税(通常は約20%の税金がかかる)
長期的な資産形成に有利
制度が恒久化され、非課税期間が無制限に(2024年から)
NISAについての説明は別ページで説明しますので、詳しくは、そちらをご参照下さい。
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことをいいます。自分で積み立てて運用し、60歳以降に受け取ることができる私的年金制度です。掛金の全額が所得控除の対象となり、税制優遇が受けられるのが大きな特徴です。
iDeCoの仕組み
毎月決まった額を拠出し、自分で運用商品を選ぶ(投資信託、定期預金、保険など)
60歳以降に一時金または年金として受け取る(運用成績によって受取額が変動)
iDeCoのメリット
1掛金が全額所得控除⇒所得税・住民税が軽減される
2運用益が非課税⇒NISAと同じく、通常約20%かかる税金がゼロ
3受取時にも税制優遇⇒一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除が適用
iDeCoのデメリット
60歳まで引き出せない(途中解約不可)
運用リスクがある(選ぶ商品によっては元本割れの可能性)
手数料がかかる(加入時、運用時、受取時に費用が発生)
他人資本の活用による資産形成
NISA・iDeCo、について、説明してきましたが、今度は、他人資本を活用した資産形成について説明していきます。
他人資本の活用についてですが、わかりやすく言うと、銀行等の金融機関から借り入れを起こして投資をするということです。
株や現物資産には、個人向けのフリーローンを除いて、金融機関が融資してくれるところはありませんが、唯一、不動産については、銀行は融資をしてくれます。
詳細については、よく学んでいただく必要があり、別途ご案内しますが、日本が、マネタリーベースを増加させたことにより、円の価格が下落を続け、物価が上昇を続けています。
不動産についても同じことが言えます。下落を続ける円を借りてきて、上昇を続ける現物(不動産)に投資することで、資産形成のスピードを加速させることができます。
おまけに、借入ですので、元金が減っていく分も加味するとNISAやiDeCo等の積み立てや貯蓄型の保険に入るよりも資産形成のスピードが全く違います。
但し、繰り返しになりますが、不動産投資についてよく学んでいただく必要がありますので、よく勉強していただきたいと思います。
まとめ
今回は、下流老人となる原因と対策にについてお伝えしてきましたが、「下流老人となるのは自業自得だ!」と言われないために、今回お伝えしてきた原因としっかりと向き合い、早いうちから対策をとっていく必要があります。
対策をとるにしても何から始めれば良いのかわからないという方もいます。まずは現状把握、自分の立ち位置を把握するところから始めてみてください。
繰り返しになりますが、自分の将来について起こり得る出来事について書きだしてみてください。
そのうえで、必要な情報をとることが不可欠です。必要な情報と言われてもピンとこない方も多くいらっしゃるでしょうから、お金の専門家である、信頼できるファイナンシャルプランナーに相談し、情報を得るようにしてみてください。
ファイナンシャルプランナーといえば、保険の相談するところだというイメージを持ちがちですが、独立した形で運営しているファイナンシャルプランナーは、お金に関することを総合的に教えてくれます。そして、実際に実行できるように親身になって相談に乗り、良き伴走者となってくれるでしょう。
私のブログをみてくださいった方々へ。是非私のLINEをフォローしてみてください。今なら無料特典プラス無料相談をさせていただいておりますので、是非LINEフォローを宜しくお願い致します。