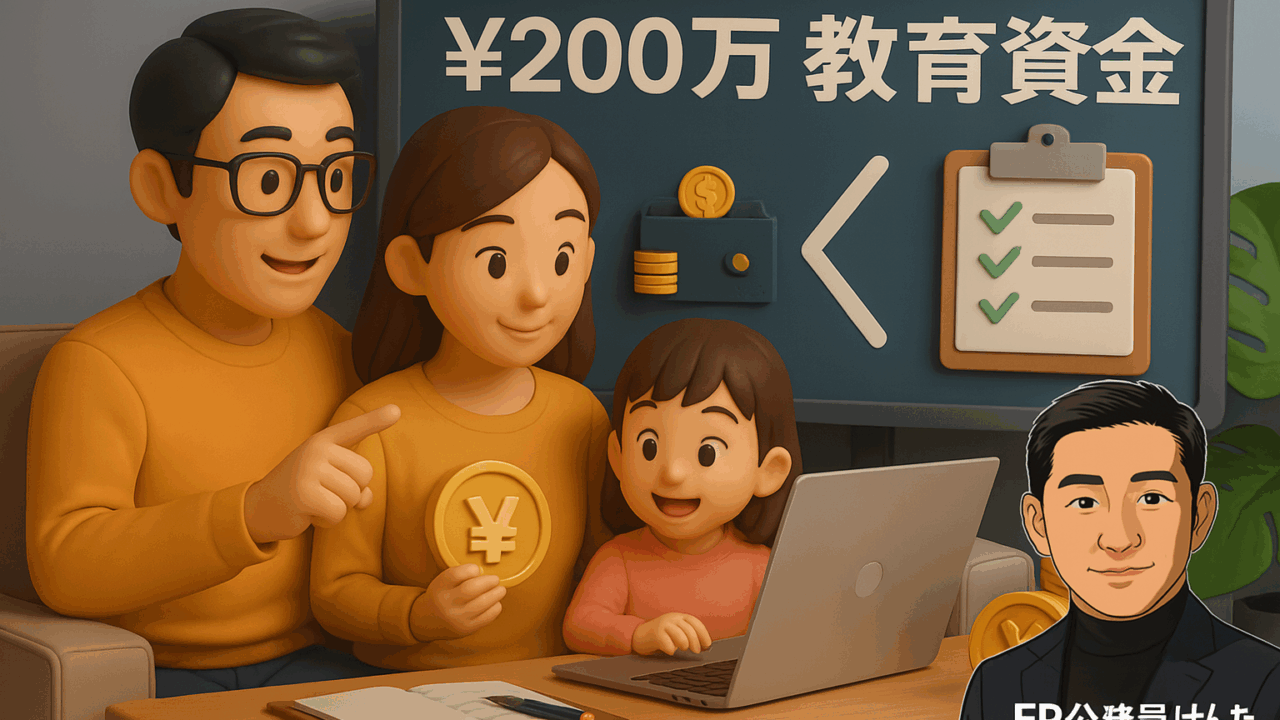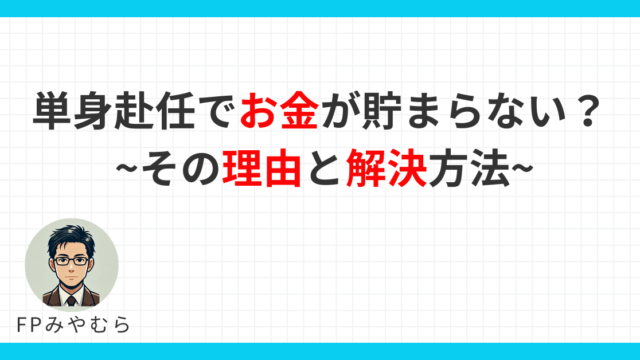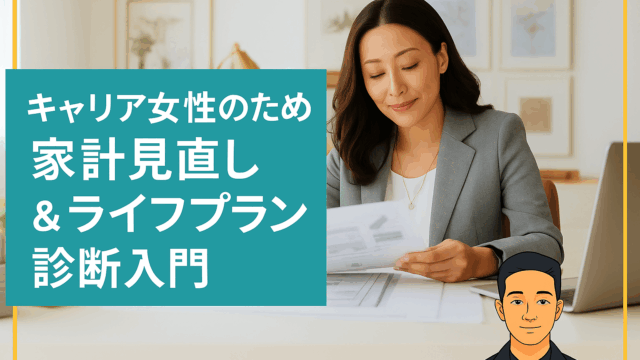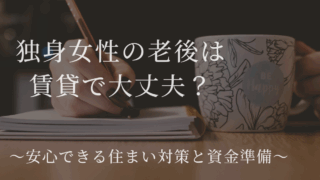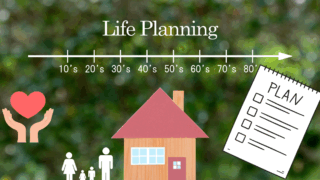子育てとお金の不安は、いつの時代も家庭に重くのしかかる課題です。特に教育費は年々高騰し、「このままで大学まで出してあげられるだろうか…」と心配する家庭も少なくありません。
この記事では、東京都在住のある30代夫婦(共働き・子ども1人)を例に、「副収入」と「節税制度」を組み合わせて、5年で教育資金200万円を確保する方法を具体的に紹介します。日々の生活を犠牲にせず、実現可能な家計戦略を学んでいきましょう。
1. 教育費の現実と不安
1-1. 子ども1人に必要な教育費はいくら?
文部科学省の統計によると、子ども1人を大学まで育てるのに必要な教育費は、公立のみの場合で約1,000万円、私立に進学すれば2,000万円を超えるとも言われています。
内訳としては、
- 小学校〜高校まで公立:約540万円
- 私立大学文系:入学金・授業料等で約700万円
- 塾や教材費、受験費用:年間50万円前後
…など、見えにくい支出も含めると、想定以上にお金がかかることが分かります。特に進学や受験のタイミングで突然発生する「イレギュラー支出」は、家計を圧迫しやすい要因となっています。
また、教育費は学費だけではありません。通学定期代、部活動費、修学旅行代、模試代なども積み重なり、想定を大きく超えることもあるのです。
1-2. 教育費に対する不安とよくある誤解
多くの家庭が「児童手当」や「学資保険」で十分だと考えがちですが、それだけでは高校〜大学にかかるコストを補いきれないのが現実です。
また、「副業は手間がかかる」「投資は危険」「節税は複雑で難しい」といったイメージで取り組みを先送りしている家庭も多く見られます。
しかし、国の制度やテクノロジーの進化により、子育て世帯が取り組みやすい副収入や節税策が数多く用意されています。今は「知って行動した人」だけが得をする時代になっています。
2. 節税制度で生まれる教育資金の余力
2-1. 子育て世帯が使える代表的な控除・制度
- 扶養控除:16歳以上の子ども1人につき38万円
- 配偶者控除/配偶者特別控除:年収103万〜150万円未満の配偶者を対象
- 医療費控除:年間10万円を超えた分が対象(確定申告)
- 生命保険料控除:年間最大12万円まで
- 小規模企業共済・iDeCo:掛金が全額所得控除
たとえば、iDeCoを月12,000円積み立てた場合、年収500万円の家庭ではおおよそ3万円の税還付が見込めます。これは「自動的に節税しながら将来資金も確保できる仕組み」として非常に優秀です。
さらに、住宅ローン控除や医療費控除なども併用すれば、所得に対する課税を大きく抑えることができ、手取りが実質的に増加します。
2-2. 「所得制限」がもたらす影響とは?
児童手当や保育料などの支援制度には所得制限が設けられており、少し年収が増えただけで支給額が減ることがあります。
たとえば、住民税所得割額が97,000円を超えると、児童手当は月15,000円から月10,000円へと減額されます。これは1年間で6万円の支給減というインパクトを持ちます。
また、自治体によっては、保育料の算定に住民税の金額が用いられるため、控除を活用して住民税を減らすことで、保育料を軽減することも可能です。
3. 子育て世帯に向いている副収入の選び方
3-1. 雇用型 vs 非雇用型の特徴と違い
副収入は大きく「雇用型」と「非雇用型」に分けられます。
- 雇用型:企業と契約して業務をこなす。時給・日給制の仕事 (例:在宅事務、コールセンター)
- 非雇用型:自身で収益をあげるフリーのスタイル(例:ブログ、ネット物販、電子書籍販売)
ある家庭では、夫が平日夜にライティング副業を、妻が育児の合間にメルカリで不要品を販売。互いに得意な分野で負担なく稼ぐことを心がけた結果、月5〜7万円程度の副収入を安定的に得られるようになりました。
時間の確保が難しい育児中こそ、非雇用型でマイペースに進められる副業スタイルが支持されています。
3-2. 実際の家庭が取り組んだ副収入例
以下は子育て家庭でも取り組みやすい副収入の一例です。
- クラウドソーシング(例:ライティング、簡単なデータ入力):月3〜5万円
- フリマアプリで不用品販売(服・育児用品など):月1〜3万円
- 積立NISA・高配当株投資:年利3〜5%のリターン見込み
- Canvaなどで作成したテンプレートの販売:1件あたり数百円〜数千円
ある家庭では、子どもの昼寝時間を活用し、Googleスプレッドシートの家計簿テンプレートを作成・販売し、3か月で1万円以上の売上になったケースもあります。
これらは初期投資が少なく、スキルも比較的不要で始められるものばかりです。
4. 節税×副収入で200万円を実現する家計戦略
4-1. 実際にいくら貯めればいいのか?
目標額200万円を5年間で貯めるには、1年あたり40万円の資金確保が必要です。月に直せば約33,000円、1日あたりにすれば約1,100円。意外と現実的な数字ではないでしょうか。
例)
- 月3万円の副収入 → 年36万円
- iDeCoや生命保険料控除などによる節税効果 → 年間約4万円
- 合計 → 年間40万円 × 5年 = 200万円
とはいえ、初年度から月3万円の副収入を安定して稼ぐのはハードルが高いかもしれません。そこでおすすめなのが「段階的積み上げ方式」です。1年目は月1万円から始め、2年目に2万円、3年目以降に3万円というように、副収入の目標額を少しずつ増やしていく方法です。
この「ステップ式」の考え方は精神的ハードルを下げ、家族全体で取り組みやすくなるという利点もあります。急に生活を変えず、できる範囲で前進することが大切です。
4-2. リアル家計のシミュレーション(共働き家庭)
モデル世帯:東京都在住の30代夫婦(夫:年収500万円の公務員/妻:年収120万円のパート)+保育園児1人
この家庭では以下の戦略を組み合わせ、教育費200万円を5年間で準備することに成功しました。
- iDeCo(月12,000円):年間約3万円の節税
- ふるさと納税(上限約6万円):日用品・食品の返礼品で年間8万円分相当を節約
- 副収入(月3万円):夫はクラウドワークス、妻はメルカリ+テンプレート販売で月収益を確保
- 副収入:36万円
- 節税:3〜4万円
- 節約:8万円相当
- 合計:47〜48万円/年 × 5年 = 235〜240万円
副収入は「お金」だけでなく、「自信」や「学び」も育ててくれます。例えば、クラウドソーシングのライティング経験がスキルアップにつながり、のちに単価の高い仕事へもつながっていく可能性があります。
また、子どもも親が働く姿を見て「お金の教育」を自然に受けられるという副次的なメリットもあります。
4-3. 確定申告で副収入を「合法的に節税」
副収入が年間20万円を超えると確定申告が必要になりますが、これは「税務リスク」ではなく「節税チャンス」です。
例えば副業で使用したパソコン(10万円)、インターネット回線費(年額約6万円)、書籍代(年間1〜2万円)などは、業務に関連していれば必要経費として計上可能です。これにより課税所得が減り、結果として納税額も下がります。
さらに、青色申告(個人事業主登録)の承認を受ければ、最大65万円の控除を受けられる制度もあります(事業規模が大きくなった場合に有効)。
最近では「freee」や「マネーフォワードクラウド」といった会計アプリが充実しており、帳簿作成や収支管理が苦手な人でも簡単に確定申告をこなせます。
節税と副収入は“合わせ技”で初めて本領を発揮します。小さくても構いません。まずは「収入源を1つ増やす」ことから始めてみましょう。
5. まとめ
教育資金の準備は、もはや「預金だけ」では間に合わない時代になりました。しかし、副収入と節税制度を正しく活用することで、家計に無理なく200万円を作ることは十分に現実的です。
しかも、その過程で「支出の見直し」や「制度の理解」「スキルアップ」など副次的な恩恵を多く得ることができます。子どもの進学資金を確保しながら、家族全体で成長できる——それが本記事で紹介した戦略の最大の魅力です。
まずは、次の3つから始めてみましょう。
- 手取りを増やすための節税制度(iDeCo・控除)をチェック
- すぐにできる副業(テンプレ販売・クラウドソーシング)を探す
- 年間の目標金額を「逆算」で計算して家計戦略に落とし込む
教育資金の不安は、行動することでしか解消できません。5年後、「あの時始めてよかった」と思えるような一歩を、今日から踏み出してみてください。
📘 無料プレゼントのご案内
🎁この記事を読んで「自分もちゃんと備えなきゃ」と思ったあなたに、『資産形成スタートガイド(PDF)』を無料でプレゼント中です!
- 年金・退職金の見込み額が分かる
- NISA・iDeCoの活用方法がわかる
- 老後に必要な資金のシミュレーション付き
こちらから受け取り可能です👇 不安を「数字で見える化」して、安心な将来への第一歩を踏み出しましょう。