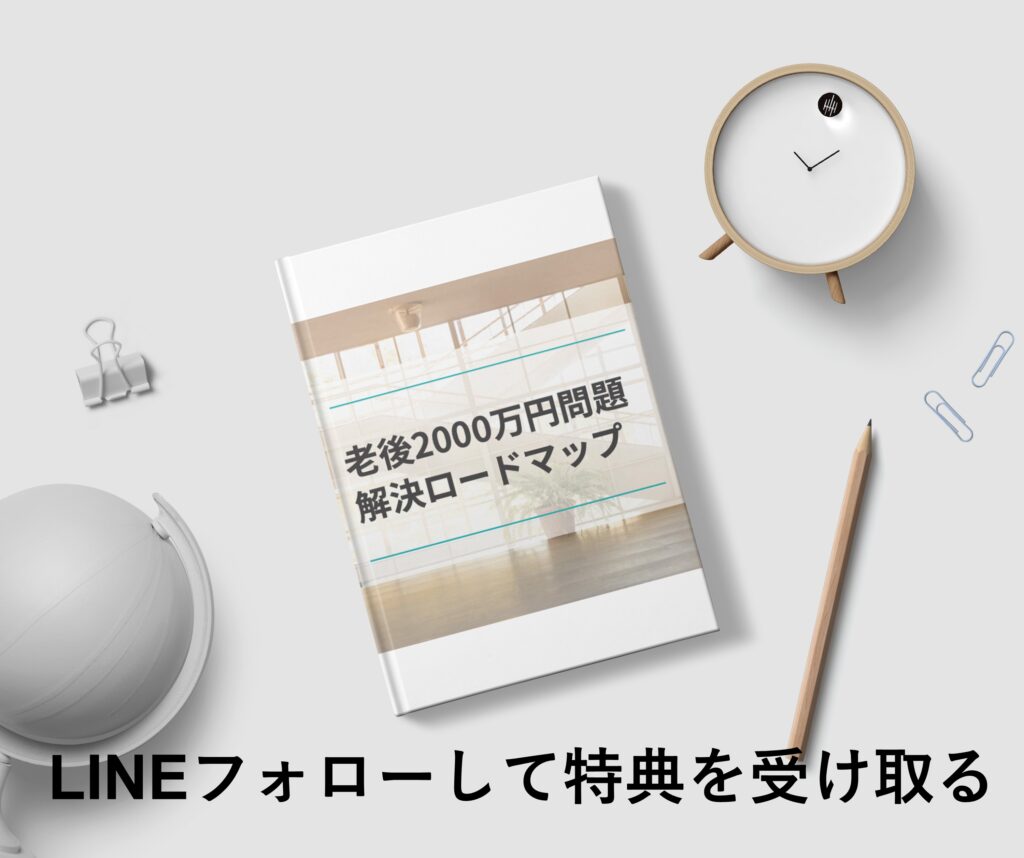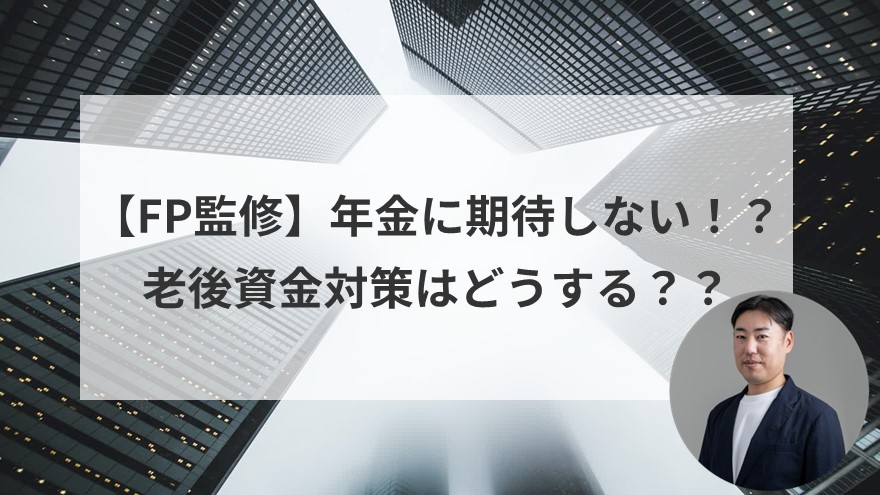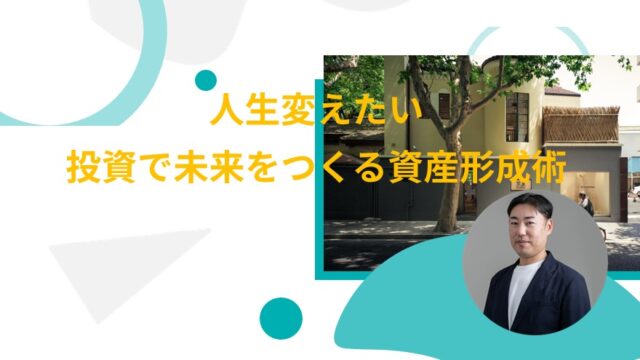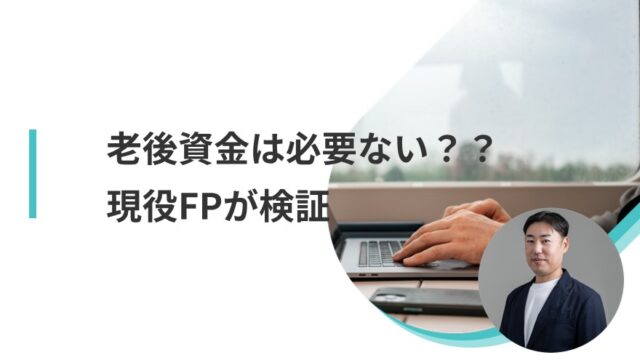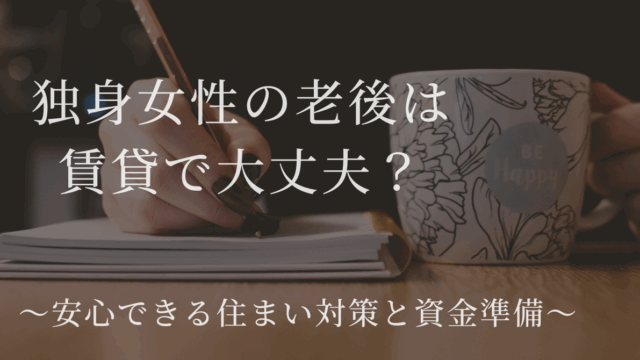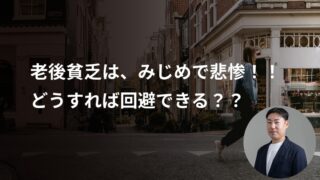「老後資金2000万円問題」は、よくTVやネットのニュース等で取り沙汰されてきましたが、「Smart research」の調査によると、
20~50代男女で年金に対する期待値を割合にしてみると、「十分な額が受給できると期待している」4.4%「必要最低限の生活ができる額を期待している」23.8%「不安定な経済状況での生活を覚悟している」30.0%「全く期待していない」が41.9%と年金に対する期待値が思っているよりも低いことがわかります。また、老後資金として、どのくらいの準備を予定しているかを調査すると、「500万円未満」7.5%「500万円~1000万円」15.0%「1000万円以上~2000万円未満」15.6%「2000万円以上~3000万円未満」15.3%「3000万円以上」15.0%「準備する予定はない、わからない」31.6%と具体的に準備しようとしている人と全く意識していない人との差が激しくわかれていることが見て取れるかと思います。
今回は、年金に期待しない人に向けて、老後資金対策をせず、このままで大丈夫かどうかクラクションを鳴らすべく、元銀行員(約7年勤務)であり、現役のファイナンシャルプランナーが、年金に期待しないで、かつ老後資金対策をどのようにすれば良いのかについて記載していきたいと思います。
この記事を最後まで読むことで、年金に期待しないでも老後安定した生活を送ることができるようになります。
公的年金制度とは?
そもそものお話にはなりますが、公的年金制度についてお話していければと思います。
厚生労働省より、「日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。
また、3階部分として、企業が任意で設立し社員が加入する「企業年金」や、国民年金の第1号被保険者が任意で加入できる国民年金基金などがあります。」自営業者や無職、学生の方は、第1号被保険者となり、加入する制度は、国民年金のみとなります。
会社員、公務員等は第2号被保険者となり、加入する制度は、国民年金と厚生年金になります。専業主婦等は、第3号被保険者に分類され、国民年金のみとなります。
国民年金とは?
もう少し深堀して、国民年金について話します。
国民年金のみに加入する人(第1号被保険者)が月々納付する年金保険料は定額(2024(令和6)年度時点で16,980円)です。
2004(平成16)年度から保険料が段階的に引き上げられてきましたが、2017(平成29)年度に上限(2004年度価格で16,900円)に達し、引き上げが完了しました。
また、2019(平成31)年4月から第1号被保険者に対して産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、2019(令和元)年度分より、2004(平成16)年度価格で保険料が月額100円引き上がり、17,000円になりました。
国民年金(基礎年金)の支給開始年齢は65歳で、納付した期間に応じて給付額が決定します。
20歳から60歳の40年間すべて保険料を納付していれば、月額6.8万円(2024(令和6)年度)受給することができます。
60歳から65歳になるまでの間でも、希望すれば給付を繰り上げて受けること(繰上げ受給)ができます。
ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、年金額は減額されたまま一生変わりません。
逆に、65歳で請求せずに66歳から70歳までの間で老齢基礎年金を繰下げて請求すること(繰下げ受給)もできます。この場合、繰下げの請求をした時点に応じて年金額が増額されます。
なお、2020(令和2)年の年金制度改正で、2022(令和4)年4月から繰下げ受給できる年齢の上限が70歳から75歳になりました。
厚生年金とは?
厚生年金は、会社などに勤務している人が加入する年金です。保険料は月ごとの給料に対して定率となっており(2017(平成29)年度以降18.3%)、実際に納付する額は人により異なります。
また、厚生年金は事業主(勤務先)が保険料の半額を負担しており(労使折半)、実際の納付額は、給与明細などに記載されている保険料の倍額となります。
従来の支給開始年齢は60歳でしたが、段階的に引き上げられ、2025(令和7)年度(女性は2030(令和12)年度)には65歳になります。
厚生年金も基礎年金と同様に、受け取る時期を繰り上げたり繰り下げたりすることができます。
このとき、繰上げ受給すると年金額が減額され、そのまま一生変わらないこと、繰下げ受給すると年金額が増額されることも基礎年金と同じです。
公的年金制度の給付額はどうやって決めているの?
日本の公的年金制度における給付額の調整方式ですが、物価スライド方式とマクロ経済スライド方式とがあります。
1. 物価スライドとは?
「目的」
年金の実質的な購買力を維持するために、年金額を物価の変動に応じて調整する為です。
「仕組み」
• 物価が上昇すれば年金額も上がり、物価が下落すれば年金額も下がります。
• 具体的には、前年の物価(または賃金)の変動率に基づいて、翌年度の年金額を改定すします。
• 物価と賃金のどちらを基準にするかは、その時点の状況によります。
2. マクロ経済スライドとは?
「目的」
少子高齢化による年金財政の悪化を抑えるために、年金の伸びを抑制します。
「仕組み」
• 物価や賃金が上昇しても、年金額の上昇率を一定割合(マクロ経済スライド調整率)だけ抑えられます。
• 調整率は、「現役世代の減少率」と「平均余命の伸び」に基づいて計算されます。
• 物価が下落した場合は、マクロ経済スライドの適用は見送られます。
違いのまとめ
| 物価スライド | マクロ経済スライド | |
| 目的 | 年金の購買力を維持する | 年金財政の安定化 |
| 基準 | 物価や賃金の変動 | 少子高齢化の影響を考慮 |
| 調整の方向 | 物価に連動して増減 | 上昇幅を抑制 |
| 特徴 | 物価の上昇時に年金額も上がる | 物価が上がっても年金の伸びが抑えられる |
実際の運用:通常は 「物価スライド」 を基本として年金額を改定し、物価が上昇した場合でも 「マクロ経済スライド」 により給付の伸びを抑制する仕組みになっています。
すべては、なぜこんなにややこしくしているのか、すべては、年金財政の安定化のためです。
結局年金っていくらもらえるの?
年金の受給額は人によってもらえる額が違ってきます。
厚生労働省の発表によると、令和元年時点では、国民全員が受け取れる老齢基礎年金の平均受給額は、月額56,049円、老齢厚生年金と合計した合計受給額の平均は146,162円となっています。
なお、厚生年金の保険料は収入に応じて納める金額が変動し、その分老後に支給される受給額も増減します。
例えば、65歳以上男性の受給権者の合計受給額の平均は月額171,305円ですが、女性は月額108,813円と差が見られます。
これは、女性は結婚や子育てによる退職などによって勤務期間が短くなりやすく、それに伴い総収入が少なくなったことが理由として考えられます。
定年退職後の支出について
定年退職後の支出は、主に生活費・医療費・娯楽費などに分けられます。
収入が年金中心になるため、支出の管理が重要になります。以下、主な支出項目とその内訳を紹介します。
1. 生活費(基本的な支出)
• 食費:自炊中心なら抑えられますが、外食が増えると負担が増大。
• 住居費:持ち家なら固定資産税・修繕費、賃貸なら家賃がかかる。
• 水道光熱費:電気・ガス・水道など。高齢になると冷暖房の使用量が増える傾向。
• 通信費:スマホやインターネットの契約。格安SIMにすることで節約可能。
2. 医療・介護費(年齢とともに増加)
• 健康保険料:75歳未満は国民健康保険、75歳以上は後期高齢者医療制度。
• 医療費:診察料・薬代・人間ドックなど。高額療養費制度を活用可能。
• 介護費:要介護状態になった場合の施設費や訪問介護費。
3. 趣味・娯楽費(充実した生活のため)
• 旅行費:国内・海外旅行の費用。
• 趣味の費用:スポーツ・文化活動・交際費など。
4. 車両関連費(車を持つ場合)
• 車の維持費:ガソリン代、保険、車検、税金など。
• 免許返納後の移動費:タクシーや公共交通機関の利用。
5. 冠婚葬祭・贈与
• 孫や子供への支援:教育資金やお小遣い。
• 葬儀費用・お墓代:自身や配偶者の準備。
支出の平均額(参考)
総務省の統計によると、高齢夫婦世帯(無職)の平均支出は月22~26万円程度。
収支逆転?支出過多の老後
ここまで、年金制度、年金収入と定年退職後の支出について触れてきましたが、お気づきの通り、平均値でみると、老齢厚生年金の受給額が、月額約17万円で支出が、22~26万円程度と約5万円以上の赤字になっていることがわかります。
老後資金の蓄えが十分にあれば、赤字でも気にしなくてよいでしょうが、老後のための蓄えが少ないとかなり厳しいところではあります。
毎月5万円の赤字×12か月=年間60万円、定年退職後30年生きたとして1800万円貯蓄が取り崩されていく形になります。
贅沢をせずに割と普通に生活してみて、5万円の赤字ですから、少し贅沢な生活をした場合、例えば、毎月10万円の赤字×12か月=年間120万円の赤字に同じく30年とすると、3600万円の貯蓄が必要になってきます。
年収500万円貯蓄300万円40歳の場合
手取りは年間約375万円~425万円程度ですので、約400万円の手取りとして考えます。仮に子一人いるとして、1か月の生活費は、
平均は30万円程度で、おもな支出項目と金額は次のとおりです。
- 住居費:2万円程度
- 水道光熱費:2万円程度
- 食費:8万円程度
- 交通・通信費:7万円程度
- 娯楽交際費:6万円程度
- 保険、医療費:1万円程度
- 家具、家事用品:1万円程度
- 衣類:2万円程度
- 教育費:1万円程度
年間で考えると、360万円の支出があり、手取り額と差し引きすると、年間で40万円程度の貯蓄ができます。
40歳から20年間貯蓄したとして、約800万円貯蓄することができます。併せて退職金が1000万円だったとすると、1800万円程度の資産形成をすることができますが、これでは、貯蓄が足りません。
こどもがもし、2人3人となってくるとさらに貯蓄ができなくなってきます。
その為にやること
貯蓄額の不足を補うべくやるべきこととして以下のことがあげられます。
現状を把握する:具体例や平均値等で示してきましたが、まずは、現状の収支を把握するところから始めてください。
未来に起こり得ることを予想する:住宅の修繕、車の買換え、医療費等、起こり得るすべてのことを書き出してみてください。
どんな生活をしたいのかを考えてみる:月に1回は旅行に行きたい、高級車に乗りたい、子どもが独立するので、小さな家に住み替えたい等、要望は人それぞれあるかと思います。
今回の例の場合は、1800万円の貯蓄をすることができますが、よりよい生活水準を送るために、は3000万円程度ほしいところでしょう。
残り、1200万円捻出するためには、どのような方法があるのでしょうか。
分散して資産形成をする
NISA、iDeCo等での資産運用:昨今は、積立式での資産運用もできるようになってきているので、活用することは必須です。
外貨建て資産の保有や現物資産の保有:アベノミクスにより、マネタリーベースが増加してきています。
簡単にいうとお金が世に出回っている総量が増え、円の価値が下落してきています。結果として、物価上昇が今後も続く見通しであり、現物資産を保有しておくことも有効な資産形成の手段といえるでしょう。
また、インターネット等で調べていただくとわかるのですが、米国の成長率は、安定的であり、ドル建ての資産を保有しておくことも必須といえるでしょう。生命保険等で約10%程度の運用成績を出しているものも外貨建てのものではでてきています。
不動産投資
現物資産の中で唯一銀行融資を受けられるのが、不動産です。
長期的な目線でみた時に、仮に途中で売却したとしたら物価の上昇とローンの残債との差額部分が手許の資産として残ります。
2000万円の物件を購入し、年間の物価上昇率が少なく見積もって2%とした場合、40歳~60歳まで保有した場合、40%の物価上昇と考えると約800万円程度得をすることになり、おまけに残債を加味すると税金やローンを35年で取り組んでいたことを加味したとして、最低でも1000~1500万円程度は、手許資金として残ることになります。
とはいえ、立地や物件によって、実現性が異なるため、よく勉強、情報収集が必要になってきます。
これらの運用方法で、1800万円しか貯蓄できなかったものが、3000万円程度まで資産を形成することができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。年金は期待しないと考えられている方でも、老後資金の対策はしっかりと行っていきたいものです。
今回の記事を読んで、実際に行動を移せば安定した老後を送ることができるかと思います。
とはいえ、自分一人でこれらを行うのは、ハードルが非常に高いと思う方もいらっしゃるでしょう。
そんな場合は、信頼できるファイナンシャルプランナーに相談してみてください。ファイナンシャルプランナーは、お金の総合的な専門家です。自分一人で悩んでいても時間は過ぎるばかりで、どんどん、資産作りをするタイミングを逃してしまいます。
私のブログを拝見してくださった皆様へ。是非私のLINEをフォローしてみてください。今なら無料特典プラス無料相談を行っておりますので、是非LINEフォロー宜しくお願い致します。