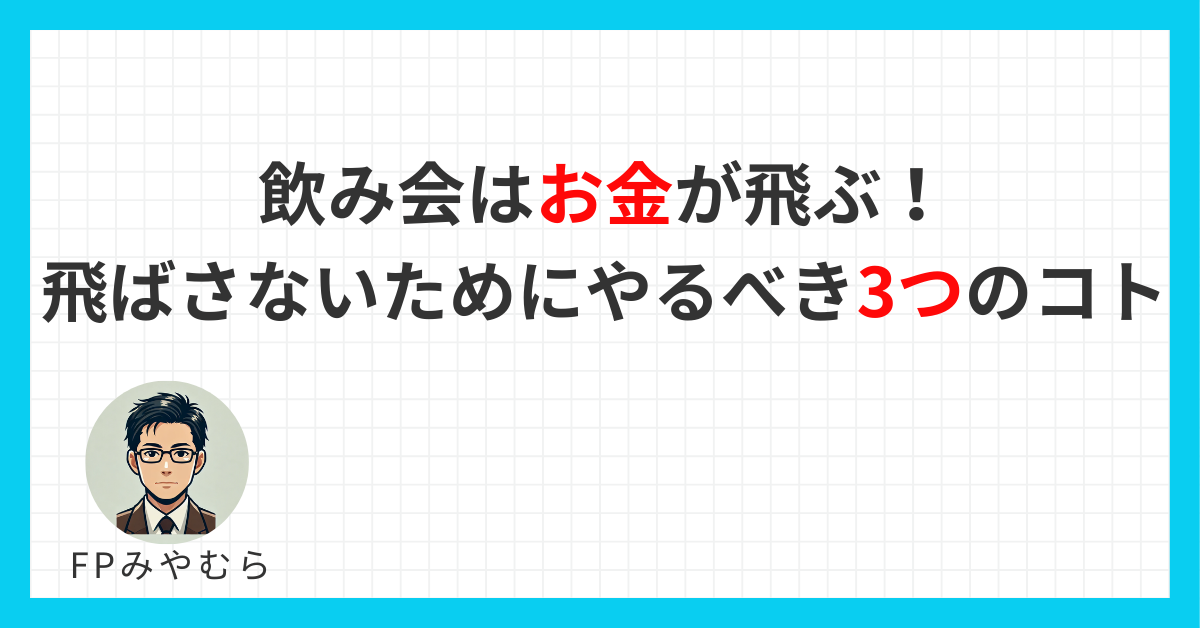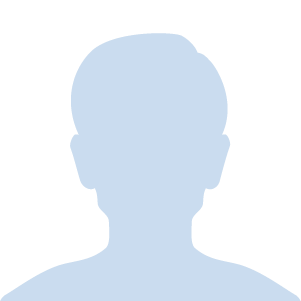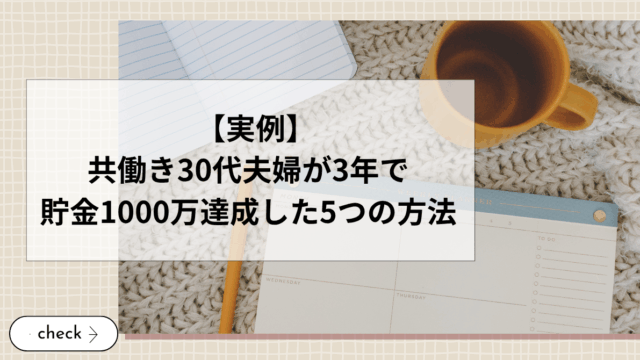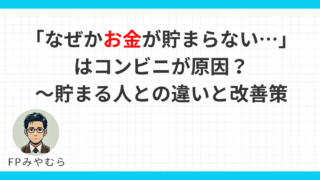こんなお悩みありませんか?
将来のために資産を増やしたいのに、飲み会代がブレーキになっていると感じている人は少なくありません。
この記事では、飲み会でお金が飛ぶ状況を防ぐための具体的な対策を紹介します。
ポイントは次の3つ。
1. 飲み会を減らすだけでどれくらいお金が浮くかを具体的に把握する
2. 健康や家族など、人間関係を壊さずに断れる理由をつくる
3. 飲み会の代替案を示しながら、自然に支出をコントロールする
本記事は、独立系ファイナンシャルプランナーとして100件以上の家計診断に携わってきたが、実践しやすい工夫をお伝えします。
読み終えたときには、
①「お金が飛ぶ飲み会」をうまく断りつつ
②人間関係も保ちながら節約できる具体的な方法
が手に入るでしょう。
是非、飲み会に消えるお金を資産形成の原資に変える第一歩を踏み出してください。
飲み会を減らすとこれだけお金が浮く
飲み会を減らすだけで、年間にすると驚くほどのお金が浮きます。
お金が浮けば旅行や自己投資、あるいは将来の資産形成に回すことができます。
統計やデータから見える飲み会の支出
総務省の「家計調査(2023年版)」によると、勤労者世帯における「外食」にかかる支出は年間およそ30万円。
その中には居酒屋での飲食費も含まれています。
さらに、リクルートの調査(ホットペッパーグルメ外食総研、2022年)では、会社員が1回の飲み会に使う平均金額は約4,500円〜5,000円とされています。
これらの数字を合わせて考えると、飲み会に参加する回数が家計に与える影響は決して小さくありません。
飲み会を減らした場合のシミュレーション
具体的に、年間でどのくらい浮くのかを計算してみます。
| 飲み会回数 | 1回あたりの費用 | 年間支出 |
|---|---|---|
| 月4回 | 5,000円 | 24万円 |
| 月2回 | 5,000円 | 12万円 |
| 月1回 | 5,000円 | 6万円 |
| 月0回 | 5,000円 | 0円 |
「月4回」を「月2回」に減らすだけで、年間12万円が浮く。
浮いたお金を投資に回せば、長期的に大きな資産形成につながる。
実例:飲み会を減らして得られた成果
ある30代会社員のAさんの例
毎週のように飲み会に参加しており、年間で約25万円を費やしていましたが、健康と家計を見直すために、飲み会を「月1回」に減らすことにしました。
その結果、1年間で約20万円が浮きました。
そのお金を積立NISAに回したところ、将来的なリターンも期待できるようになり、「飲み会を断ることが資産形成の第一歩になった」と実感。
40代の子育て世帯Bさんの例
飲み会を控えたことで、毎月の浮いた1〜2万円を教育資金の積立に回しました。
「断るのは最初は気まずかったが、習慣にしてしまえば意外と周囲も理解してくれる」と語っています。
飲み会を減らすことは、単なる節約ではなく「お金を未来に振り向ける選択」です。
月数回の飲み会を減らすだけで、年間数万円から十数万円単位でお金が浮き、そのお金を資産形成や自己投資に回すことで、将来の安心につながります。
家計管理を考える上で、まずは「飲み会の回数」を見直すことが最も効果的な節約方法のひとつですね!
健康を理由にする
「飲まないキャラ」を定着させる
飲み会で毎回「今日はたまたま飲まない」と言うと、周囲からは「次回は飲むかもしれない」と思われがちです。
その結果、断りづらくなり、結局出費も増えてしまいます。
最も効果的なのは「自分は基本的にお酒を飲まない人」というキャラを定着させることです。
厚生労働省の「国民健康・栄養調査」(令和5年)によると、
20歳以上の男性の約16%、女性の約8%が「ほとんど飲まない」と回答
つまり「飲まないキャラ」は少数派ではあるものの、確実に一定数存在しており、社会的にも受け入れられています。
例えば、毎回ノンアルコール飲料を頼み、「自分は飲まない人です」という姿勢を一貫して示せば、次第に周囲もそれを前提に接してくれるようになります。
乾杯は炭酸水、会計はしっかり割り勘に応じれば、人間関係を壊さずに「飲まないキャラ」を浸透させられます。
このようにキャラを定着させることで、毎回の説明や気まずさを減らし、飲み会の出費を自然に抑えることができます。
ダイエット・睡眠を理由にする
飲み会を断るときに「ダイエット中」や「睡眠を大切にしている」と伝えるのも効果的です。
お金の問題を直接言うよりも、健康や自己管理を理由にした方が角が立ちません。
国立健康・栄養研究所のデータ:
日本人成人の約3割がBMI25以上の「肥満傾向」にあり、特に30~40代男性の割合が高い。
厚生労働省の「国民健康・栄養調査」:
20~50代の多くが「睡眠不足」を自覚していると報告されています
これらは多くの人が共感しやすい理由です。
「最近ジムに通い始めたのでお酒は控えている」とか「睡眠の質を上げたいから夜遅くまで飲まないようにしている」と言えば、周囲も理解しやすいでしょう。
飲み会の翌日のだるさを避けられるだけでなく、体調管理と節約を両立できます。
医者や健康診断を引き合いに出す
「健康診断で数値が悪かった」や、「医者にお酒を控えるように言われた」のように医師や健康診断の結果を根拠に説明すると、説得力が増し、相手は強く否定できません。
厚生労働省の「令和4年 国民健康・栄養調査」より
肝機能に関わるγ-GTP値が高い人の割合は男性で約15%、女性で約5%にのぼる。
⇒医者から「飲酒を控えるように」と指導される人は決して少なくない。
例えば「最近、肝臓の数値が少し高めで控えています」と言えば、誰も無理に勧めてきません。
さらに「健康第一で」と添えると、相手も納得しやすくなります。
このように医者や健診を理由にするのは、社会的に強力な「盾」として使える方法です。
結果的に飲み会の参加頻度や支出を減らせるだけでなく、自分の体調管理にも直結します。
家族やプライベートを優先する
「家庭時間」を盾にするのは最強の理由
家庭やプライベートを理由に飲み会を断ることは、最も理解されやすい方法の一つです。
特に日本では「家庭を大事にすること」は社会的に肯定的に捉えられやすく、相手に不快感を与えにくい特徴があります。
30代から40代は「家族との時間を優先したい」と考える傾向が強く、飲み会よりも家庭を重視する傾向が年々強まっています。
つまり「家族と過ごす時間があるので参加できません」と伝えるだけで、相手も納得しやすいのです。
・「子どもと夕食を一緒にとることにしているので」
・「週末は家族で過ごすことにしています」
・「妻(夫)と約束があるので」
実際の場面では、このように表現するのが有効ではないでしょうか?
また、こうした言葉は単なる断り文句ではなく、相手に「大切なことがあるのだな」と思わせる効果があります。
結果として、人間関係を壊さずに飲み会を回避でき、同時に出費も抑えることが可能になります。
趣味や習い事を予定に入れる
家庭の理由以外にも、自分の趣味や習い事を理由に断るのも効果的です。
・社会人が週に1回以上行っている趣味・学習活動の平均時間は2時間以上で、リスキリングや健康志向を背景に増加。
⇒「趣味や習い事に時間を使う」という理由が、社会的に一般的になっていることを示しています。
総務省の「社会生活基本調査」より
断り文句としては、例えば、
・「ジムに通う日なので」
・「英会話のレッスンがあるので」
・「資格の勉強会があって」
のようなものが考えられます。
ここでのポイントは「前から決まっている予定」という雰囲気を出すことです。
飲み会は突発的に決まることが多いため、「すでに組み込んでいる予定」を示すのは、相手との関係性を壊すことなく飲み会を避けるのに有効です。
プライベート優先を自然に伝えられる雰囲気を作る
断るときだけ「家庭」や「趣味」を理由にするのではなく、日常的に「自分はプライベートを大事にしている人」という雰囲気を周囲に伝えておくことも大切です。
約6割の社会人が「ワークライフバランスを意識している」と回答。
⇒プライベート優先のスタイルは珍しいことではなく、むしろ一般的な考え方になりつつある
リクルートの「働く人調査」より
実例としては、日頃の会話で
・「週末は必ず家族と過ごすことにしている」
・「平日は運動や勉強の時間を確保している」
といった自分のスタイルを軽くシェアしておくことです。
そうすれば、飲み会の誘いがあったときに「やっぱり彼(彼女)はそういうタイプだ」と自然に理解してもらえます。
結果として「断る」のではなく「自分らしい生活を優先している」と認識され、人間関係を壊すことなく節約を実現できます。
代替案を提示するのもアリ
飲み会を断るときにただ「行けません」と伝えるだけでは、人間関係に角が立ってしまうことがあります。
そこで役立つのが「代替案」を提示する方法です。
単純に断るのではなく、別の形で交流の機会を提案すれば、節約と人間関係の両立が可能になります。
次に紹介する方法は、実際に多くの人が活用している現実的なアイデアです。
二次会は行かない
一次会で楽しく過ごしたあとに「二次会は遠慮します」と伝えるだけで、出費は大幅に減ります。
総務省の家計調査(2023年)によると、交際費の平均支出は1世帯あたり年間で約32万円にもなる。
特に飲酒を伴う交際費は一回あたりの金額が大きく、二次会に行くかどうかで大きな差が生まれます。
・一次会だけなら出費は3,000~5,000円程度
・二次会に行くとさらに3,000円以上追加
・月2回断るだけで年間7万円以上の節約効果
実際に「二次会は行かない」と決めてから家計が安定したという声も多く、節約の第一歩として効果的です。
飲み会からランチ会にすり替える
「飲みたい気分ではないけど交流は大事」という人には、ランチ会を提案する方法があります。
ランチなら1,000円前後で済むため、夜の飲み会の3分の1以下に収まります。
日本フードサービス協会の外食統計(2024年)によると、
夜の居酒屋利用単価は平均3,500円に対して、ランチ利用は平均900円程度と大きな差がある。
ランチ会に替えることは、お金と健康の両方を守れる賢い方法です。
「短時間」の参加にする
「最初の1時間だけ顔を出します」とあらかじめ伝えておく方法も効果的です。
飲食代は滞在時間に比例する部分が大きいため、乾杯に参加して場を盛り上げつつ、早めに退席すれば自然と支出も減ります。さらに翌日の体調や睡眠リズムにもプラスになります。
【工夫例】
・最初の乾杯と食事だけ参加
・「翌朝予定がある」と理由をつける
・1時間で退席すれば出費は半額近くに抑えられる
「全く行かない」とは違い、参加の姿勢を見せながら節約できる
ちょい飲み系の定食屋に行く
「飲みたいけど節約したい」ときは、居酒屋より安い“ちょい飲み系”の定食屋を提案するのもおすすめです。
近年はチェーン店でも1杯とおつまみをセットにした、いわゆる“せんべろ(千円でベロベロ)”メニューが充実しています。
個人が外食にかける平均額は夜で2,500円前後。
ちょい飲み系定食屋なら1,000円台で楽しめるケースも多くある。
ちょい飲み系定食を選択するメリットは、
・お酒1杯+小鉢で1,000円台
・定食も頼めるので栄養バランスが良い
・「飲みたい派」と「食べたい派」の両方を満たせる
無理なく交流を続けつつ、財布にもやさしい選択肢になります。
人間関係を壊さずに上手に飲み会を断って節約しよう
まず大切なのは「断る=人間関係が壊れる」ではない、という考え方です。
言い方や工夫次第で、相手に嫌な印象を与えずに飲み会を減らすことは十分可能です。
むしろ自分の立場をきちんと伝えられる人は、信頼されやすいという面もあります。
節約や家計管理のために飲み会を断るのは、立派な自己管理の一環といえるでしょう。
相手への配慮を欠かさない
飲み会の誘いを断るときに一番大切なのは「丁寧さ」です。
例えば、
・「誘ってくれてありがとう。実は今は出費を抑えていて…」
・「ごめん、今週は予定があって難しいんだ。またの機会に!」
といった形で、まずは感謝や前向きな言葉を添えることが相手の心証を和らげます。
まとめ
飲み会を断ることは、人間関係を壊す行為ではなく、自分の暮らしを守るための大切な選択です。
・感謝を伝える ・代替案を用意する
・一貫した態度を貫く
これらを意識すれば、相手も理解してくれやすくなります。
節約と信頼関係を両立させることができるのです。
飲み会は楽しい時間でも、その裏でお金が飛んでしまいがち。
無理なく断る工夫をすれば、節約と人間関係の両立は可能です。
あなたの将来計画を実現するためなら、飲み会との付き合い方を見直すことが大切です。
最後にポイントを整理します。
1. 飲み会は大きな出費になりやすい
2. 健康や家庭を理由に断りやすい
3. 代替案を出すと人間関係も円滑
4. 節約は資産形成の第一歩
お金を無駄に飛ばさず、未来のために備える行動を始めましょう。
もっと具体的な家計改善のヒントは、私のLINE公式に登録する事で手に入ります。今なら、無料面談の特典もつきます。
無駄をなくしたい!
どうやって、飲み会を避けるのか具体的に相談したい!
という方は、下のボタンを押してLINE公式に登録してください!