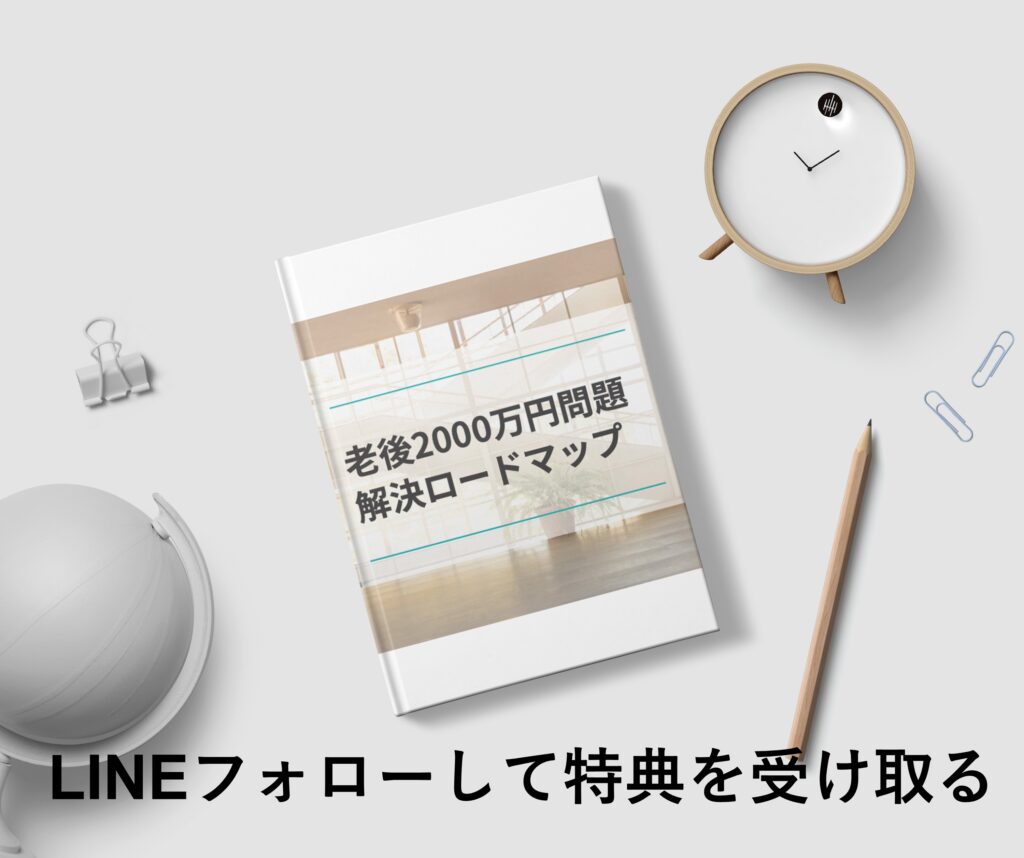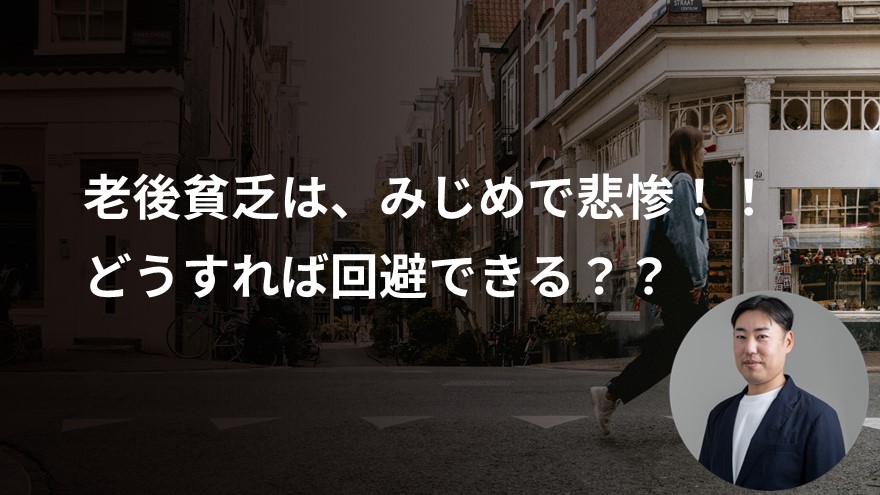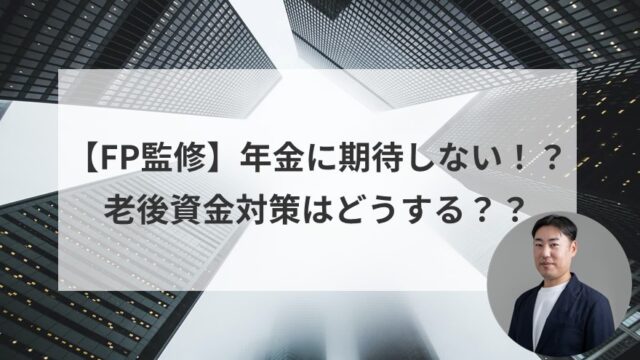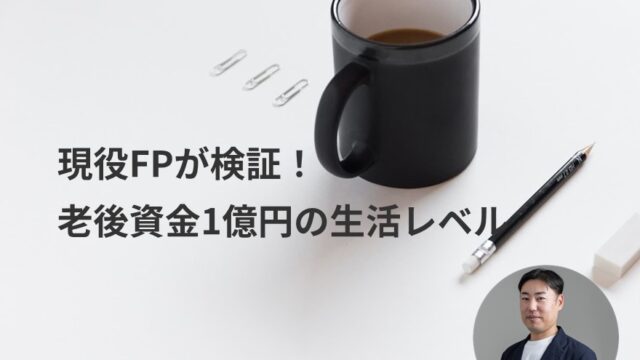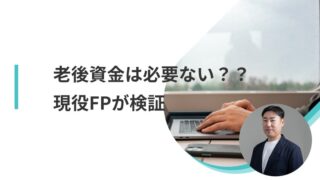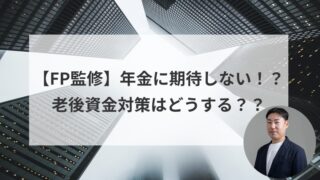「老後貧乏でみじめな生活を送りたくない」そんな考えをお持ちの方がおおくいらっしゃるのでは、ないでしょうか。
近年、物価高や、年金の受給額の減少、受給時期の繰延など、「これからの日本の老人たちは、どうなっていくの?」と疑問におもうこともあるでしょう。
また、老後貧乏と呼ばれ、みじめな生活を送ることに対して不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
本記事では、金融機関にて7年勤務した、現役のファイナンシャルプランナーが、老後に不安のないみじめな生活を回避する方法について記述しています。この記事を読むことで、老後貧乏になることはなくなるでしょう。
老後貧乏・みじめな生活に陥る人の5つの特徴
老後貧乏・みじめな生活に陥る人の5つの特徴についてご説明していきたいと思います。
借金返済が家計を圧迫している
住宅ローンや高金利のカードローン、リボ払いを利用している人は、要注意です。
カードローンは、利息が高く、毎月の返済のほとんどは、利払いに充てられてしまします。高齢になってからの住宅ローンの取り組みも要注意です。
65歳の定年までに住宅ローンが完済する予定になっていない場合は、無職になってからも住宅ローンを払い続けなければならず、老後貧乏・みじめな生活の第一歩となるでしょう。高所得者であっても多額のローンを組むのは注意が必要です。
無駄遣いが多い
仕事ができる現役時代に収入があるからといって、無駄遣いが多すぎると、思った程、老後への備え、貯蓄ができず、現役引退後に余裕のある生活ができなくなってしまい、節約生活を送ることになってしまいます。
収入があるうちは、ピンとこないかもしれませんが、老後無職になったとたん、一気に無駄遣いのツケがまわってきてしまいます。
収入以上の生活をしている
当たり前の話かもしれませんが、結構できていない方もいらっしゃいます。
ゴルフ等の趣味や仕事のストレスによる飲み代等が膨れ上がり、自制できていない方もいらっしゃます。
お金の専門家である金融機関で勤めていた私の同僚でさえも、収入以上にお金を使いすぎてしまって支出過多になってどうしようもなくなってしまっている方も何人もみてきています。
投機※1やギャンブルに失敗している
私は、パチンコや競馬等のギャンブルをしないので、気持ちがわかりませんが、資産を増やそうと、ギャンブルに走る人はかなり危険です。
オンラインカジノの還元率は97%、パチンコでも80〜85%とかなり高くみえるので、表面上の控除率と還元率だけをみると「損しにくそう」と感じるようになっています。
控除率(※2) | 還元率 | |
| パチンコ | 15〜20% | 80〜85% |
| オンラインカジノ | 3% | 97% |
| 競馬 | 20〜30% | 70〜80% |
| 競輪 | 25% | 75% |
| 競艇 | 25% | 75% |
ところが、上記の数値には落とし穴があります。たとえば、1万円をオンラインカジノに使用して還元率が97%であれば、平均的には9,700円が戻ってくる計算です。
一見、たった300円の損失にみえますが、1,000回繰り返すと30万円、1万回繰り返すと300万円の損失につながります。また、パチンコでも同じ原理が働き1万円使用すれば、平均的に8,000円〜8,500円しか戻ってきません。
つまり、最初から1,500円〜2,000円を失う前提でお金を入れているようなものです。
オンラインカジノだと数秒、パチンコでも数十分でお金を動かせるため、利用者は「損を早く取り戻さないと」という心理が働き、より繰り返しお金を投機しやすくなる仕組みになっています。
そのため、運営側としては3%〜20%と控除率を低く見積もっていても元が取れる仕組みとなっています。
このように還元率が高くみえても必ず運営側の取り分(控除率)が上回り、トータルでは損するのが投機やギャンブルの本質です。
今まで稼いできた資金を失わないためにも、生活費を投機やギャンブルばかりに使わず、余裕資金で資産運用したり、貯金したりして老後破産のリスクを減らしましょう。
(※1)投機とは「確率」にお金を投じること、投資とは「価値」にお金を投じること
(※2)控除率とはギャンブルを主催する企業や団体の「手数料および利益」
上記、ライジングブル公式ブログより、引用
生活支出が収入を上回っている
現役世代では、なかなか考えにくいかもしれませんが、この特徴は、老後のお話です。
老後の夫婦での年金支給額の平均は、23万円程度です。
家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)結果の概要によると、65歳以上の無所得世帯がかかるお金の平均と内訳は以下のとおりです。
| 夫婦世帯 【平均額(円)/構成比(%)】 | 単身世帯 【平均額(円)/構成比(%)】 | |
| 食費 | 67,776(28.6) | 37,485(26.2) |
| 住居費 | 15,578(6.6) | 12,746(8.9) |
| 光熱費・水道代 | 22,611(9.6) | 14,704(10.3) |
| 医療費 | 15,681(6.6) | 8,128(5.7) |
| 交通費・通信費 | 28,878(12.2) | 14,625(10.2) |
| 被服・履物 | 5,003(2.1) | 3,150(2.2) |
| 家具・家事用品 | 10,371(4.4) | 5,956(4.2) |
| 娯楽・教養 | 21,365(9.0) | 14,473(10.1) |
| その他 | 49,433(20.9) | 31,872(22.3) |
| 消費支出合計 | 236,696(100) | 122,559(100) |
合計支出の他にも、非消費支出として税金や保険料の支払いなどがプラスされるため、さらにお金がかかります。
と考えると、老後無職となると支出の方が上回ることが考えられるので、足りない部分を貯蓄から取り崩して生活していかなければなりません。
老後貧乏・みじめな生活に陥らない方法5選
老後貧乏・みじめな生活に陥らない方法として5つまとめてみましたので、ご覧ください。
老後に向けた資産運用をする
まずは、老後に向けた資産運用を検討してみましょう。現役世代からのちょっとした行動で、老後貧乏になることを防ぐことができます。
とはいえ何から始めてよいのかどんな考え方で、行動すればよいのかなどわからない部分もあるかと思いますので、簡単に経済動向について触れていきたいと思います。その上で資産運用を検討してみましょう。
アベノミクスによるインフレ
アベノミクスとは、安倍元総理が表明した「3本の矢」を柱とする経済政策のことです。最大目標を経済回復と位置づけ、
①大胆な金融政策(デフレ脱却を目指し、2%のインフレ目標が達成できるまで無期限の量的緩和を行うこと)
②機動的な財政出動(東日本大震災からの復興、安全性向上や地域活性化、再生医療の実用化支援等に充てるため、大規模な予算編成を行うこと)
③民間投資を喚起する成長戦略(成長産業や雇用の創出を目指し、各種規制緩和を行い、投資を誘引すること)
という3本の矢によって、日本経済を立て直そうという計画です。この計画に沿って政策が動いてきたため、インフレが今になり、顕著に表れてきています。今後も、量的緩和政策は続くので、物価高による収支の悪化は、進むでしょう。
年金問題(物価スライドとマクロ経済スライド)
「物価スライド」と「マクロ経済スライド」は、いずれも年金制度における調整ルールですが、目的や調整の仕方が異なります。以下にわかりやすく違いを整理します。
物価スライドの目的は、年金の実質的な価値を保つことで、調整基準は、物価または賃金の変動です。年金を受け取る人の生活水準を維持するために物価の上昇に連動させて年金額も引き上げるというもので、基本的には、前年の物価の変動に合わせて年金額を調整します。
一方、マクロ経済スライドは年金制度の持続可能性(財政の健全化)を保つことが目的です。調整基準は、物価または賃金の変動-スライド調整率(少子高齢化を反映)となります。
高齢化により、年金受給者が増え、支える現役世代からが減ることに対応するため、年金の伸びを抑える制度です。
ザクっというと「物価や賃金が上がっても」そのままの割合では増やさず、少し抑えて年金額を調整するものです。例えば、物価がプラス2%でもスライド調整率が1%なら、年金はプラス1%しか増えないという感じです。
近年は、マクロ経済スライドに移行しており、アベノミクスによるインフレに対して年金額の増加が追随していくことは、なかなか考えにくいでしょう。
上記のアベノミクス、マクロ経済スライドを意識した上で、資産運用を考えてみてください。
資産運用の方法として、お勧めするのは以下の通りです。
NISA・iDeCo等での資産運用
NISAとは、少額投資非課税制度といい日本の個人投資家向けの税制優遇制度で一定額までの投資に対して売却益や配当金が非課税になる仕組みです。
NISAには、2種類の枠があります。
1積立投資枠
長期・分散投資向け
対象商品:金融庁が認めた投資信託やETFのみ
非課税期間 無期限
年間投資上限120万円
2成長投資枠
個別株や幅広い投資信託も対象
非課税期間 無期限
年間投資上限 240万円
NISAのメリット
売却益や配当金が非課税(通常は約20%の税金がかかる)
長期的な資産形成に有利
制度が恒久化され、非課税期間が無制限に(2024年から)
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことをいいます。自分で積み立てて運用し、60歳以降に受け取ることができる私的年金制度です。
掛金の全額が所得控除の対象となり、税制優遇が受けられるのが大きな特徴です。公務員でもiDeCoの加入が認められています。
iDeCoの仕組み
毎月決まった額を拠出し、自分で運用商品を選ぶ(投資信託、定期預金、保険など)
60歳以降に一時金または年金として受け取る(運用成績によって受取額が変動)
iDeCoのメリット
1掛金が全額所得控除⇒所得税・住民税が軽減される
2運用益が非課税⇒NISAと同じく、通常約20%かかる税金がゼロ
3受取時にも税制優遇⇒一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除が適用
iDeCoのデメリット
60歳まで引き出せない(途中解約不可)
運用リスクがある(選ぶ商品によっては元本割れの可能性)
手数料がかかる(加入時、運用時、受取時に費用が発生)
ハイスピードでできる資産形成
NISA、iDeCoよりもハイスピードで資産形成できる方法として不動産投資が挙げられます。
不動産投資により取得した物件は、家賃収入が自身の所得となるため、個人年金保険の役割をはたしてくれます。
高所得者や公務員の方であれば、ローンも通りやすいので、より区分所有マンションであればより多くまたは、マンション1棟等の物件を組むことができます。
人口動態等をよく調べて、立地の選定を間違わなければ、家賃収入の増加を見込むことができます。
また、個人年金保険とは違い、家賃収入に加えて「不動産」という現物資産を保有できることもメリットです。
不動産を含む現物資産は、国の政策もあり、上昇を続ける見通しです。さらに、不動産に関しては、管理は不動産管理会社に任せることができるため、毎日の本業で忙しく、投資に時間を割くことが難しい高所得者が取り組みやすいのです。
借金問題は早急に解決する
住宅ローンや、カードローン、その他フリーローンなどがある場合は現役世代の余裕があるうちに早期に解決しておくべきでしょう。
ムダな固定費を削って貯金をする
毎月の固定費、最近では、サブスク等も出てきていますが、無駄だなと思っていることは、ありませんか。
人間新しく始めることには積極的でも、手放すことに対しては、消極的になりがちです。定期的な断捨離をすることをお勧めします。
周りに流されない
マインドセットのお話になりますが、人間良くも悪くも、どうしても人と比べてしまいがちです。人に飲みに誘われても、2次会3次会までとだらだら行くのではなく、少しで良いので節約する意識をもつことがたいせつでしょう。また、見栄を張りすないよう自分を律する意識づけも必要であると思います。
健康を維持して長く働く
現役世代でのストレスケアや老後孤立した状況を作らないことも健康を維持していくことが大切です。健康を維持し、マンションの管理人等簡単な仕事で、収入源を確保しつつ長期で働ける環境について考えてみましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
老後貧乏でみじめな生活を送りたくないそんな方が多くいらっしゃるかと思います。この記事を読んで、少しでも老後に良い生活を送ることができる人が一人でも多くなることを切に願っています。私たちファイナンシャルプランナーはお金の専門家です。自分で情報収集しているけど、なかなか行動に起こせない方への伴走や、勉強方法等お金の面でのアドバイスをしています。是非一度ご相談いただけると幸いです。
私のブログを拝見してくださった方々へ。是非私のLINEをフォローしてみてください。今なら無料特典プラス無料相談を行っておりますので、是非是非LINEをフォローしてみてください。