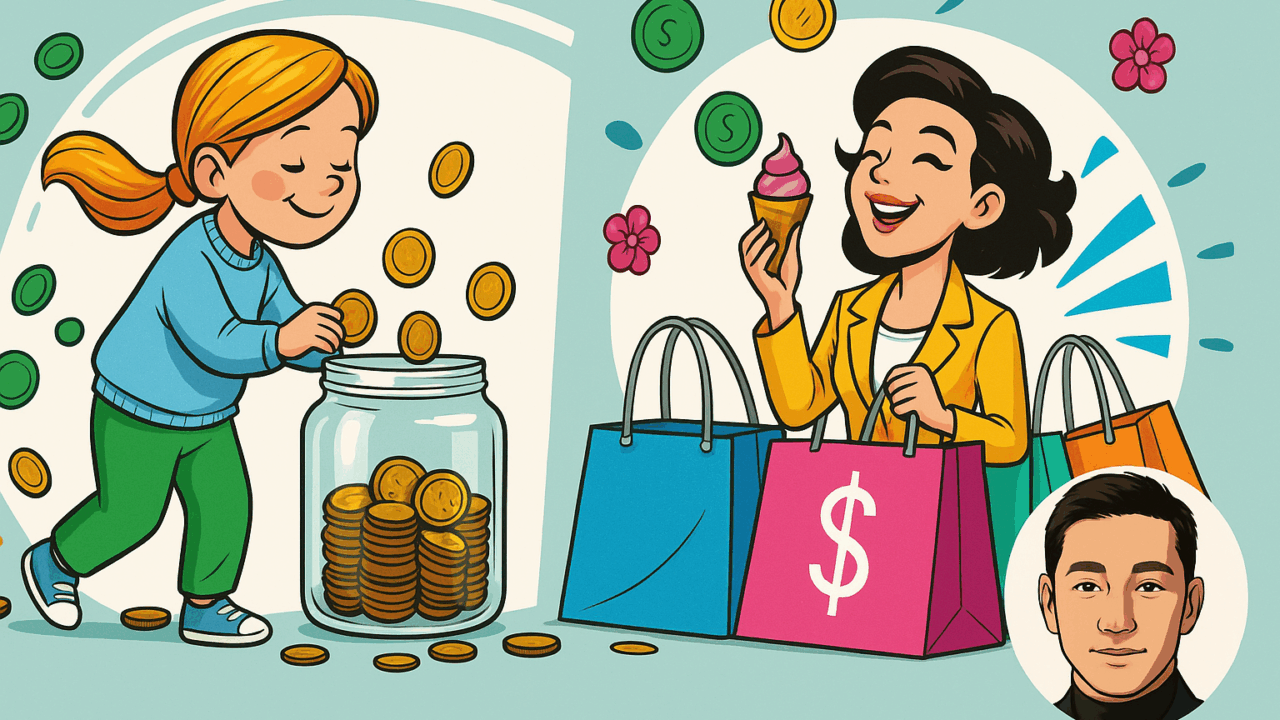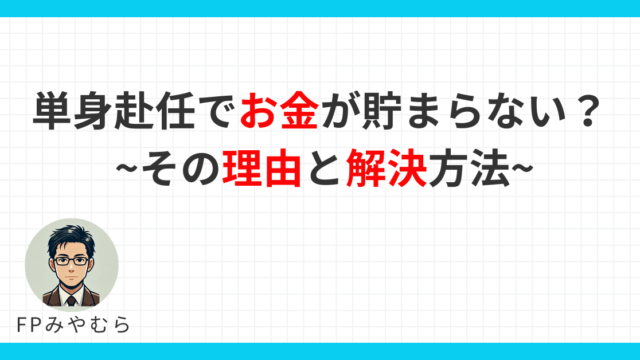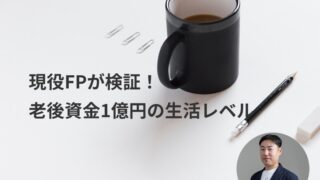「お金を貯めようと思っているのに、なぜか毎月ギリギリになる…」そんな経験はありませんか?
資産形成において「知識」や「収入」も大切ですが、実は“お金の使い方のクセ”があなたの未来を大きく左右します。
「貯めグセ派」と「使いグセ派」、どちらの傾向が強いのか?そして、その傾向に合った資産形成のスタートとは?
本記事では、行動経済学の視点からお金との付き合い方を見直し、誰でも取り組める第一歩をお伝えします。診断コンテンツも紹介していますので、自分の行動パターンを知り、今日から資産形成を始めていきましょう。
なぜ「お金のクセ診断」が資産形成に有効なのか
1-1. お金の行動には“無意識”が潜んでいる
「ついコンビニで無駄遣いしてしまう」「SALEの文字を見ると財布のひもが緩む」―こうした行動の多くは、無意識のパターンによって繰り返されます。人間の脳は、できるだけエネルギーを使わず判断しようとするため、過去の習慣や感情が優先されがちです。
つまり、意志の力だけで貯金や投資を継続するのは難しいということです。まずは、自分が「どんな状況で、なぜお金を使うのか」「何に価値を感じやすいのか」といった“クセ”を客観視することが、正しい資産形成のスタート地点になります。
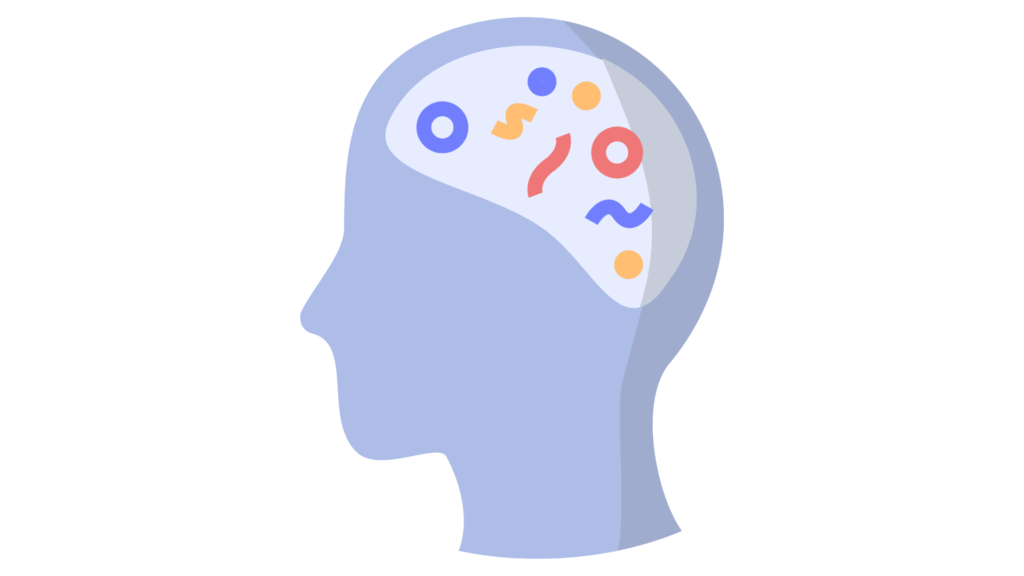
1-2. 行動タイプを知れば「続く仕組み」が作れる
たとえば「使いグセ派」は、楽しみながら取り組むことが長続きのカギ。一方で「貯めグセ派」は、数値化や目標設定をすればコツコツ続けやすい傾向があります。
このように、タイプごとに合った習慣形成のアプローチが異なるため、診断を通じて自分のスタイルを把握し、それに適した工夫を取り入れることで、無理なく資産形成が定着していきます。
1-3. 行動経済学から見る「お金のクセ」の正体
資産形成の行動には、「合理的に判断しているつもりで、実は感情に左右されている」場面が多く見られます。これは「行動経済学」の分野でも明らかになっており、たとえば『現状維持バイアス』という心理傾向があります。これは、現状を変えることに強い抵抗を持ち、たとえ将来的に得になるとわかっていても、新しい習慣や制度に手を出さない心理です。
もうひとつ有名なのが『プロスペクト理論』。これは、人が「損を避けたい」という気持ちに強く支配される傾向です。たとえば、1万円の利益を得るよりも、1万円の損失を防ぐことに強く反応してしまう。これにより、損をしたくないがために資産運用の機会を逃すこともあります。
貯めグセ派・使いグセ派それぞれの特徴とは?
2-1. 貯めグセ派の特徴と傾向
貯めグセ派は、以下のような特徴を持ちます。
- 買い物前に必ず比較検討する
- 「将来の安心」に強い価値を感じる
- 家計簿アプリの使用率が高い
こうした人は、積立NISAやiDeCoといった長期投資と相性が良く、節税効果を活かして計画的に資産を増やせます。
2-2. 使いグセ派の特徴と傾向
一方で使いグセ派には、以下の傾向が見られます。
- 直感で「欲しい!」と感じたらすぐに行動する
- 「今を楽しむこと」に重きを置く
- セールやSNS広告に弱い
このタイプは「貯金=我慢」ではなく、「楽しく貯める」仕組みが必要です。たとえば、ゲーム感覚で貯金できるアプリの活用や、リターンが見える短期投資が向いています。
2-3. あなたはどっち? あるある行動パターン
(A)貯めグセ派|30代・地方公務員男性|悠太さんの場合
悠太さんは家計簿アプリを毎日チェックし、スーパーでは必ず値段を比較してから購入。貯蓄率は高めだが、株式投資やNISAに踏み出せないまま数年が経過している。
このようなタイプは「失敗したくない」という気持ちが強く、知識の習得には熱心でも、実行には時間がかかりがち。対策としては、「月1万円だけNISAで積立てる」といった小さな習慣から始め、経験値を積むことが効果的です。
(B)使いグセ派|40代・共働き主婦|真理子さんの場合
真理子さんは日々忙しく、スマホの広告で見た便利グッズをついポチってしまうことが多い。旅行やカフェなど「体験」にお金をかけることに価値を感じるタイプ。
このようなタイプは「今を楽しむこと」がモチベーション。だからこそ、楽しみながらできる「ポイント運用」や「ゲーム感覚貯金」が有効です。
行動タイプに合った資産形成のスタート方法
3-1. 「貯めグセ派」向けのおすすめ戦略
貯めグセ派には、以下のような方法が効果的です。
・目標金額を明確にし、期間で区切って可視化
・毎月固定額の自動積立(つみたてNISA・定期預金)
・支出カテゴリを分類し、予算超過を防ぐ仕組み作り
特に「自動化」は大きな味方です。たとえば、給与口座から投資用口座へ毎月定額を移す設定をしておけば、「残ったら貯める」という思考から、「最初に貯めて残りで生活する」という前向きなスタイルに変わります。
また、貯めグセ派は「計画的であるがゆえに慎重すぎる」という一面も。完璧を求めるあまり、投資や副業など新たなステップを踏み出せないことがあります。その場合は、「月1,000円から投資を体験してみる」「まずはNISA口座を開設するだけ」など、極小ステップで動いてみることが有効です。行動を積み重ねることで「やればできる」という成功体験が得られ、習慣化のスピードが上がります。
さらに、貯めグセ派は数字やグラフで進捗を確認できるとモチベーションが維持しやすくなります。可視化に優れた家計管理アプリやポートフォリオ追跡ツールを使うことで、「資産形成が進んでいる実感」が得られやすくなります。
3-2. 「使いグセ派」向けのおすすめ戦略
使いグセ派には、「お金の使い道に満足しながら貯まる仕組み」を作るのがポイントです。
・“〇〇したら〇〇貯金”など、行動連動型の貯金
・ポイント運用やキャッシュレス決済のリターン活用
・貯めた額を「見える化」するアプリを併用する
たとえば「コンビニに寄らなかったら500円貯金」など、小さな成功体験をルール化すると楽しく継続できます。貯金の動機を「制限」ではなく「楽しみ」として捉えることで、ストレスなくお金が貯まっていきます。
また、使いグセ派は「未来の安心より、今のワクワク」を重視する傾向があります。そこで「今すぐ使えるご褒美制度」を設けると効果的です。たとえば「1万円貯まったらカフェで好きなスイーツを食べていい」といった、小さなインセンティブを自分で作るのもアリです。
さらに、SNSや友人との共有もおすすめです。貯金額を写真で記録してシェアしたり、貯金仲間と「今月のチャレンジ」を決めて競い合ったりすることで、外発的モチベーションが刺激されます。

3-3. 習慣化のコツは「環境」と「仕組み」
資産形成において、「始める」よりも大切なのは「続ける」ことです。では、続けるためには何が必要か?
答えは「環境」と「仕組み」の2つです。
たとえば、テレビの横に家計簿アプリを開いたスマホを置いておく、冷蔵庫に「今月の貯金額」を書いたメモを貼っておくなど、日常生活の中に「貯金を意識するトリガー」を設置するのが効果的です。
そして、仕組みの中でも最も強力なのが「自動化」です。お金の移動を手動で行うと忘れる可能性が高くなりますが、給与からの天引きやアプリの自動引き落とし機能を活用すれば、意識せずとも資産が積み上がっていきます。
一方、使いグセ派には「行動を記録して可視化する」習慣が有効です。習慣化アプリや貯金アプリを使って、日々の小さな行動(節約、無駄遣いをしなかった日など)を記録し、「見える達成感」を積み上げることで、自己肯定感も高まります。
3-4. 行動変容を支える「小さな成功体験」
資産形成を継続する上で見落とされがちなのが、「小さな成功体験」を積み重ねることの重要性です。人間は、自分の努力が何らかの成果に結びつくと実感できたときに、次の行動へのモチベーションが高まります。
たとえば、1か月間で1万円の積立ができた、週に1回のノーマネーデー(お金を使わない日)を実践できたなど、些細なことでも構いません。
重要なのは、「できた自分」を認識し、自信を積み重ねることです。
これを実現するためには、定期的に振り返りの時間を設けることが有効です。日記に記録をつけたり、家族やパートナーと成果を共有したりすることで、行動が可視化され、成果を実感しやすくなります。
3-5. 外部の力を借りて、継続の仕組みを強化する
「自分一人ではなかなか続けられない」という方には、外部リソースの活用もおすすめです。たとえば、家計簿アプリを利用して定期的に通知を受け取る仕組みを作る、SNSで“貯金チャレンジ”を発信して仲間と共有するなど、他人の目やサポートがあると行動の継続率が大幅に上がります。
また、FP(ファイナンシャルプランナー)に一度相談して自分に合ったプランを作成するのも効果的です。プロの視点から具体的な数値目標や対策をアドバイスしてもらえることで、曖昧だった資産形成の方針が明確になります。
行動タイプ別のアプローチだけでなく、行動を続ける「支援装置」を取り入れることで、日々の習慣が着実に定着していくでしょう。
診断から始める!あなたの資産形成タイプを知ろう
4-1. 行動診断で資産形成を「自分事」にする
最も重要なのは「自分はどのタイプなのか」を理解することです。一般的なアドバイスよりも、自分の性格や行動傾向に沿った情報の方が、納得感があり、継続につながります。
4-2. 資産形成診断はこちら
まずはあなたの「お金のクセ」をチェックしてみましょう。以下のリンクから診断を受けてみてください。
まとめ
資産形成は、「性格に合った仕組みづくり」が成功のカギです。貯めグセ派・使いグセ派といった行動傾向を理解し、それぞれに合った方法を選べば、無理なく・長く続けられます。まずは診断から、自分の“クセ”を知ることが第一歩です。今日の気づきが、将来の安心につながります。
📘 無料プレゼントのご案内
🎁この記事を読んで「自分もちゃんと備えなきゃ」と思ったあなたに、『資産形成スタートガイド(PDF)』を無料でプレゼント中です!
- ✔ 年金・退職金の見込み額が分かる
- ✔ NISA・iDeCoの活用方法がわかる
- ✔ 老後に必要な資金のシミュレーション付き
こちらから受け取り可能です👇 不安を「数字で見える化」して、安心な将来への第一歩を踏み出しましょう。