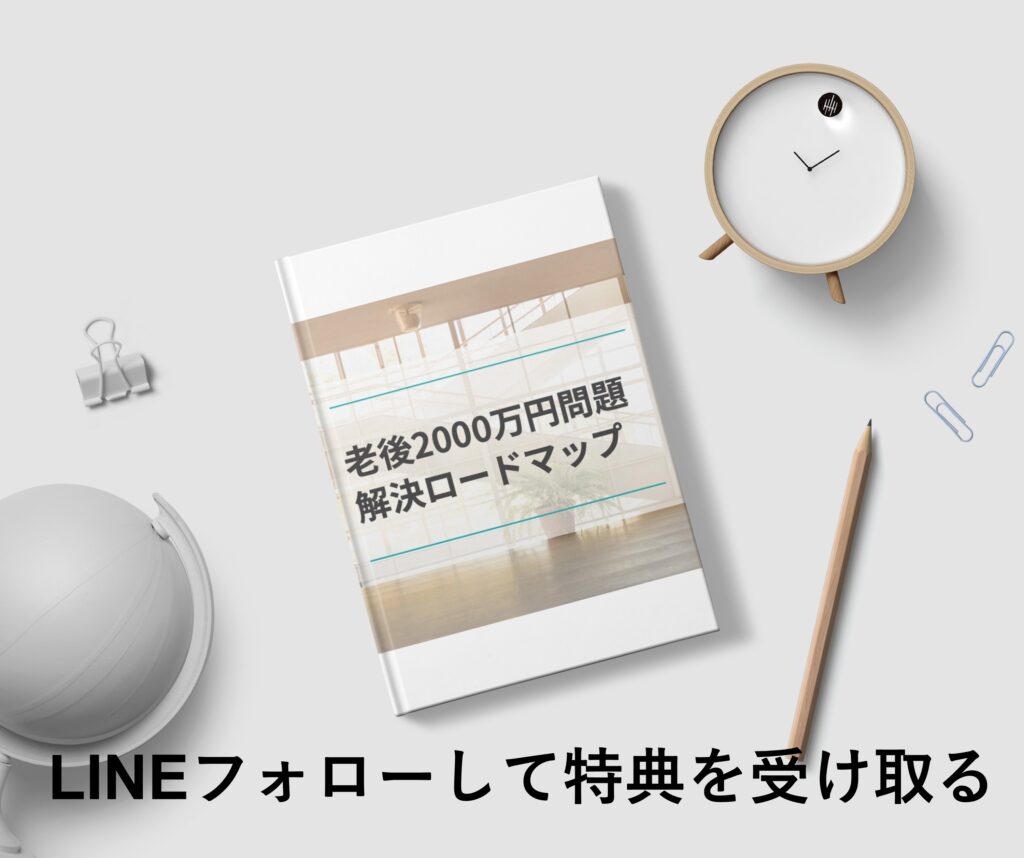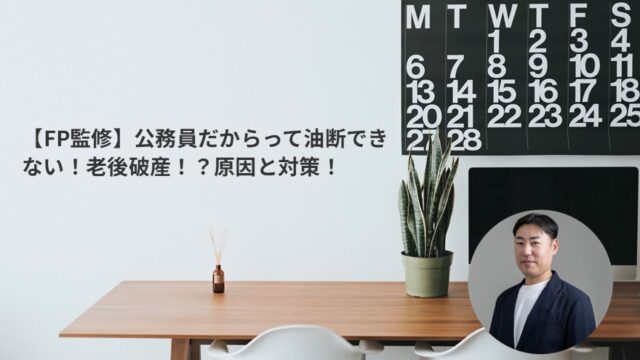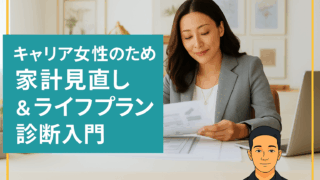昨今、NISAやiDeCo等貯蓄から投資へという動きが高まり、資産形成について関心を持ったり、政治や経済についてもニュースでよくチェックするようになってきているかも知れません。
今回は、どストレートに資産を守る方法について、元銀行員であり、現役FPである私が、資産を守る方法について解説していきたいと思います。
資産形成について
実際に、資産形成はこれからの時代を生き抜いていく上で、非常に重要です。
資産を増やすことはもちろん大切な考え方ではありますが、資産を増やすことばかりに目を向けすぎてしまうと、いざという時に資産を守ることはできません。
最悪の場合資産を大きく減らしてしまう事になりかねません。
経済について大昔を振り返る
経済についてバブル絶頂の頃を思い出して見てください。または、思い浮かべてみてください。
若い世代の方は、あまりピンとこないかもしれませんが、郵便局で定期貯金をすると10年で約倍になるなど、放っておいてもお金が増える時代でした。
それをスポーツに例えるとすると、野球の時代だとします。おまけに不動産等現物資産に投資しているとどんどんと増えていっていました。
投資で資産を増やしていった好事例としては、西武グループ等が有名ですね。
経済について少し前を振り返る
失われた10年ないし20年と言われるように、バブルが弾け、金融機関の合併や破綻が相次ぎ、経済が低迷していく世の中に入っていきます。
スポーツに例えるなら野球からサッカーに急に分野が変わった状態になっていきます。皆こぞって安全な資産、預金へ資産を移すことが当たり前になり、「投資は怖い」となっていきます。
アベノミクスについて
2012年のお亡くなりになられた安倍元総理の時代に遡りますが、アベノミクスにより、円の価値及び、物価上昇が始まったことも老後破産の原因の一つとして挙げられます。
そもそも、アベノミクスとは、安倍元総理が表明した「3本の矢」を柱とする経済政策のことです。最大目標を経済回復と位置づけ、①大胆な金融政策(デフレ脱却を目指し、2%のインフレ目標が達成できるまで無期限の量的緩和を行うこと)、②機動的な財政出動(東日本大震災からの復興、安全性向上や地域活性化、再生医療の実用化支援等に充てるため、大規模な予算編成を行うこと)、③民間投資を喚起する成長戦略(成長産業や雇用の創出を目指し、各種規制緩和を行い、投資を誘引すること)という3本の矢によって、日本経済を立て直そうという計画です。
この計画に沿って政策が動いてきたため、インフレが今になり、顕著に表れてきています。今後も、量的緩和政策は続くので、物価高による収支の悪化は、進むでしょう。
老後2000万円問題について
金融庁が令和元年にまとめた「金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書」で発表されたモデルケースでは、老後資金が2,000万円不足するとも言われ、物議を醸しました。
報告書一部抜粋↓↓
「夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職の世帯では、毎月の不足額の平均は約5万円であり、また20~30年の人生があるとすれば、不足額の総額は、単純計算で1300万円~2000万円になる。この金額はあくまで平均の不足額から導き出したものであり、不足額は各々の収入・支出の状況やライフスタイル等によって大きく異なる。当然不足しない場合もありうるが、これまでより長く生きる以上、いずれにせよ今までより多くのお金が必要となり、長く生きることに応じて資産寿命を延ばすことが必要になってくるものと考えられる。重要なことは、長寿化の進展も踏まえて、年齢別、男女別の平均余命などを参考にしたうえで、老後の生活において公的年金以外で賄わなければいけない金額がどの程度になるか考えてみることである。」
今後は、野球→サッカー→ラグビーの時代に移っていきます。
今後の経済の見通しについて
日本は、現在インフレ率年間で2%を目指しています。簡単にいえば、毎年2%ずつ物価が上がっていく状態を目指しており、実際に2023年には平均で3.1%以上物価が上昇しました。
インフレ率2%を目指すといいながらも3%上昇したりとインフレが今後も続いていくとすると、現在の100万円は20年後には60~50万円程度になってしまいます。
つまり、現金を今まで通りに貯金していると、いつのまにか現金が半分程度まで減っている状態になりかねません。
今やるべきこと
では、まず今何からやればいいのかについてお伝えしていきます。
まずは、自分の現在地を知る
経済の流れについてはざっくりとでも掴んでいただけたはずなので、自分事に置き換えて考えてみましょう。まずは、自分の現在地について知ることが必要です。
現在自分には、資産がどのくらいあり、どのくらいの収入があって、どのくらいの支出があるのかを見ていく必要があります。収入が多い方にありがちなのが、クレジットカードでの支払い任せで、支出についてあまり関心を持っていないことが多いので一度意識してみて下さい。
そのうえでどのくらい投資に回せるのかを考えてみてください。
自分は、どこに向かいたいのかを知る
自分は、どのくらいの収入、資産を目指しているのかをできるできない気にせずに意識してみてください。書き出してみるのが良いでしょう。
参考までに、最新のデータよると、2023年時点では、純金融資産1億円以上5億円未満の「富裕層」と、5億円以上の「超富裕層」を合わせた世帯数は約165.3万世帯にのぼります。これは、2021年時点の148.5世帯から11.3%増加し過去最高となっています。総世帯数(約5,570万世帯)から見ると、全体の約2.97%にあたり、金融資産1億円以上を保有する世帯も限られたものですが、一定数いらっしゃいます。「約30世帯に1世帯は富裕層である」と考えると、意外と珍しくないような感覚にもなるのではないでしょうか。
このデータを参考に自分はどのくらいの資産が必要なのか、また、その資産でどんな暮らしがしたいのかを書き出してみると良いでしょう。
例えば、老後に世界を旅してみたい、月に1回はゴルフに出かけたい等、それぞれ理想とする未来があるはずです。理想がより明確であればあるほど、行動に移しやすくなりますので、是非お試しください。
その上でやるべきこと
経済の過去現在そして未来の展望、野球からサッカーへそしてラグビーの時代へのうつりかわりについて理解し、自分の現在地、目指したいゴール設定を行ったのであれば、そのうえでやるべきことを考えていきましょう。
積立投資
一番簡単なのは、積み立て投資ですね。毎月の収支から余力分を投資に少しずつ回し、現預金で置いておくよりも高い利回りを確保していくことで、未来の資産形成の準備を少しずつ始めていきましょう。
ちなみに資産形成は早くやったもの勝ちで、仮に約5000万円を65歳でつくることを前提に資産形成した場合、20歳から始めると、毎月26,000円、合計コスト1,404万円、35歳から始めると、毎月62,000円、合計コスト2,232万円、50歳から始めるとなんと毎月190,000円、合計コスト3,420万円とかなりの違いが出てきます。
現物資産への投資
金等現物資産への投資も有効です。最近はワインへの投資等も行われているそうです。前述の物価上昇目標2%を考えると、20年で少なく見積もっても40%もの差が表れてきます。
例えば、わかりやすく、1000万円投資したとして、20年後には、税金がかかる可能性がありますが、約400万円弱の差が表れてきます。
信用力の活用について
信用力を活用した不動産投資も大変有効です。
だいたい住宅ローンを加味したとして、年収の15~20倍程度のローンをくむことができるので、ハイスピードの資産形成を考えるのであれば、信用力を活用した不動産投資を検討することも一つです。
但し、利回り重視の不動産投資は、修繕コスト等色々と考えなければならないことが多く詐欺に近いものも多いので注意が必要です。よほど、時間やお金に余裕のある方、建築、不動産に知見をお持ちのプロの方でない限りは、利回り重視10%や15%等のものは、手を出さない方が良いです。
最近の目安としては、5%前後が目安と言えるでしょう。よく考えて勉強いただくことが大切です。
利回りを重視せず、手堅くいくなら、新築区分所有マンションへの投資がおススメです。1棟に比べて、値段が安く、利回りは高くありませんが、入退去時の修繕費もそんなにかからないうえに、管理会社に任せておけば、ほとんど手間やコストがかかりません。
また、不動産投資のメリットとしては、減価償却費等のお金が実際に出ていかない経費計上できるので、確定申告上赤字にして、給与所得と相殺できる点も魅力のひとつです。立地、特に、人口動態等をよく調べた上で、一度検討してみてください。
一人で考え込まないで相談する
ここまで、読んでいただいた方は非常に勉強熱心な方だと思います。勉強熱心な人ほど陥りやすいのが、情報迷子です。
昨今は、ネット、YouTube等で様々な方が色んな見解で話をされています。勉強熱心なのはよいことですが、一人で情報収集をし、情報迷子にならないようにすることが重要です。
また、情報迷子になることで行動が止まってしまう恐れがあるので、信頼できる中立的な視点を持った伴走者である、FPに相談することが最も得策と言えます。
まとめ
バブルからバブル崩壊後の日本経済、その後の未来の展望、野球からサッカー、ラグビーへと世の中の常識がどんどん変化していっています。
前半は日本経済を中心にご理解いただけたかと思います。
後半は、その上で、自分事として捉え、自分の現在地を知ること、そのうえでゴール、自分のありたい未来を描くことそのうえで、どのような手段を取っていけば良いのかについてお伝えしてきました。
資産形成は、中盤でもお伝えした通り、早く行動に移したもの勝ちです。情報を集めることができても、実際に行動に移すことが重要です。
頭では分かっていても行動に移せない方は、是非一度中立的なお金のプロであるFPに相談してみてください。良き伴走者となってくれます。
ここまで、お読みくださり本当にありがとうございました。相談してみたいとか、情報がほしいという方は是非LINEフォローしてください。今なら無料特典、無料相談受け付けています。