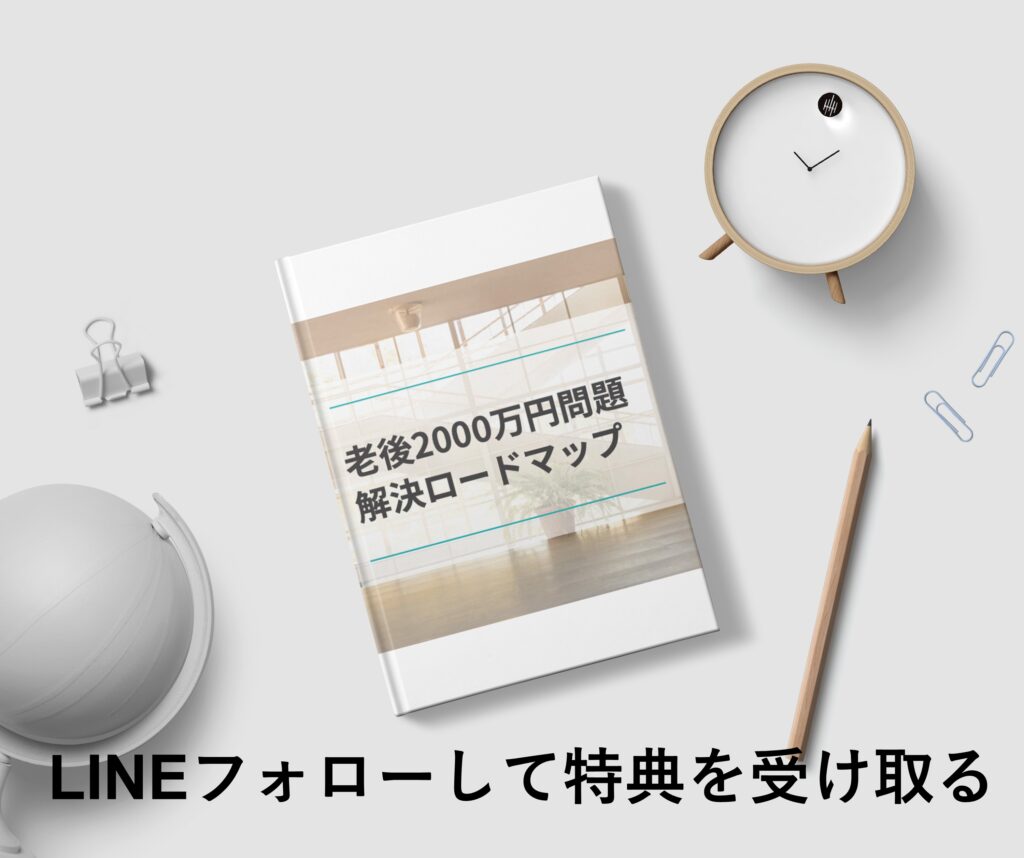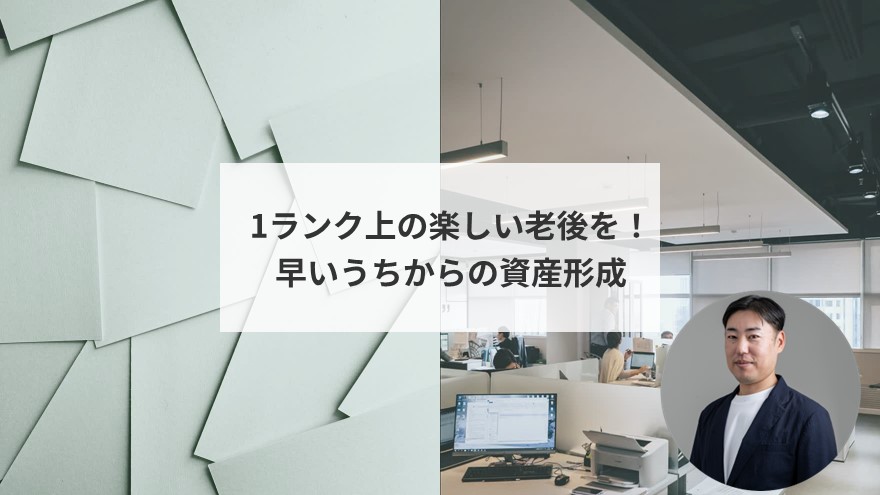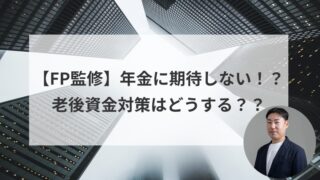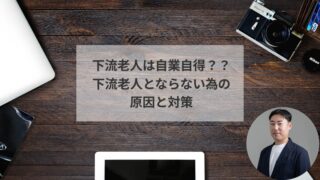定年退職後、特に後期高齢者と言われる世代になり、不安なく楽しい老後生活を暮らしたいと思っている現役世代の方々は多くいらっしゃることでしょう。
昨今、70歳くらいまでは、再雇用等の制度で働ける仕組みが作られており、収入面での心配はないかもしれませんが、その先を見据えて将来を考えていくと対策を取っている人と取っていない人で、楽しい老後を迎えることができるかどうかさがでてきます。
楽しい老後を暮らすにはどうすればよいか、それは、現役世代、早いうちからの資産形成しかありません。
貯蓄から投資へとよく言われていますが、何から始めてよいのか、どんな情報を集めればよいのかわからないかと思います。
また、発信者によってどんな投資方法が良いのか意見がバラバラで迷子になってしまうケースもあります。
今回は、元銀行員であり、現役のファイナンシャルプランナーが最期に高級有料老人ホームで迎えたい等希望を叶え、孤立など不安のない、1ランク上の楽しい老後の暮らし方のポイントをお金の観点を中心にしてお伝えしていければと思います。
1. 老後に必要なお金はいくらか?
老後に必要なお金はいくらか気になっている方も多いでしょう。老後に必要とされる資金は以下に記載していきます。
その前に現役世代の方へ、現状の毎月の収支は把握できていますか。
ざっくりとで構いませんので、現状の収支を把握した上で次の章へお進みください。
1.1. 老後の生活費の目安
総務省の「家計調査報告」によると、高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上)の平均的な生活費は、月に約25万円とされています。一方、単身世帯の場合は月15万円前後が目安となります。
しかし、これはあくまで平均的な数字であり、生活スタイルによって必要な金額は大きく異なります。
例えば、「世界一周旅行にチャレンジしてみたい」「高級車に乗ってみたい」「趣味にお金を費やしたい」など、人によって価値観が違いますが、趣味や嗜好にお金を使うには、その分の費用を上乗せする必要がありますし、持ち家か賃貸か住宅ローンが残っているのかによっても必要な金額が変わります。
1.2. 公的年金だけで足りるのか?
多くの人が老後の生活資金として頼るのが「公的年金」です。厚生労働省によると、国民年金(基礎年金)の満額は月約6万8000円、厚生年金を受給している場合は夫婦で月22万円程度が目安となります。
しかし、先述のように夫婦での生活費が月25万円必要だとすると、毎月3万円ほど不足する計算になります。 ゴルフ等お金がかかる趣味や海外旅行等、お金がかかるライフスタイルを送りたいという方は、平均値以上の不足額が出てきます。これを補うためには、貯蓄や運用、あるいは退職後の収入源を確保することが重要になります。
2. 老後資金の準備方法
では、平均値でみた場合に毎月の収支がマイナスとなってしまう場合の老後資金の準備方法について以下に示していきたいと思います。
2.1. 貯蓄の目安と方法
老後資金を準備するためには、定年までに最低でも2000万円の貯蓄が必要とされています(いわゆる「老後2000万円問題」)。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個々のライフスタイル、価値観、どんな暮らしをしたいかによって異なります。今回は、1ランク上の楽しい老後を暮らすためにどんな方法があるのでしょうか。
貯蓄の方法としては、以下のような手段があります。
積立型の貯蓄(例:定期預金、財形貯蓄)
シンプルに積立型の貯蓄です。銀行での積立や、企業が実施している財形貯蓄などもあります。
確定拠出年金(iDeCo)
自分で積み立てて運用し、60歳以降に受け取ることができる私的年金制度です。掛金の全額が所得控除の対象となり、税制優遇が受けられるのが大きな特徴です。
iDeCoの仕組み:毎月決まった額を拠出し、自分で運用商品を選び(投資信託、定期預金、保険など)、60歳以降に一時金または年金として受け取ることができます。(運用成績によって受取額が変動)
iDeCoのメリット:iDeCoのメリットは以下の3点です。
・掛金が全額所得控除⇒所得税・住民税が軽減される
・運用益が非課税
・受取時にも税制優遇⇒一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除が適用
iDeCoのデメリット:iDeCoのデメリットは以下の3点です。
・60歳まで引き出せない(途中解約不可)
・運用リスクがある(選ぶ商品によっては元本割れの可能性)
・手数料がかかる(加入時、運用時、受取時に費用が発生)
NISA(少額投資非課税制度)
日本の個人投資家向けの税制優遇制度で一定額までの投資に対して売却益や配当金が非課税になる仕組みです。
NISAには、2種類の枠があります。
・積立投資枠
長期・分散投資向け
対象商品は金融庁が認めた投資信託やETFのみとなります。
非課税期間は、無期限です。
年間投資上限120万円
・成長投資枠
個別株や幅広い投資信託も対象
非課税期間は無期限です。
年間投資上限:240万円
NISAのメリット:NISAのメリットは以下の3点です。
・売却益や配当金が非課税(通常は約20%の税金がかかる)
・長期的な資産形成に有利
・制度が恒久化され、非課税期間が無制限に(2024年から)
3. 老後の支出を抑える工夫
老後の資金の準備については、上記に示した通りですが、収支を見直すことも楽しい老後を送るために必要なことです。
3.1. 住居費の最適化
住居費は老後の支出の中でも大きな割合を占めます。
持ち家がある場合はリフォーム費用の準備が必要ですが、住宅ローンを完済していれば住居費の負担は軽くなります。
一方で賃貸の場合、家賃の負担が続くため、住み替えを検討するのも一つの方法です。
また、「リバースモーゲージ」という制度を活用し、自宅を担保に融資を受けながら生活する方法もあります。
3.2. 医療費と介護費用の備え
高齢になると、医療費や介護費用の負担が増える可能性があります。
健康保険や介護保険を活用しながら、医療費を抑える工夫をすることが重要です。
具体的な対策としては、 「高額療養費制度を活用する」「介護保険サービスを上手に利用する」「医療保険や介護保険に加入しておく」等が挙げられます。
また、日頃から栄養を意識した食事、適度な運動、人との会話等、健康管理を行うことで、将来的な医療費を抑えることもできます。
3.3. 日々の生活費の見直し
老後においては、固定費を減らすことが支出を抑える鍵となります。
節約の例:例えば以下の3つが節約の例として挙げられます。
• スマホ料金の見直し(格安SIMの活用)
• 自家用車の売却やカーシェアの利用
• 食費の見直し(自炊の工夫)
これらを実践することで、生活費を抑えつつ、無理のない老後生活を送ることができます。
4. 老後の収入源を確保する
支出については、ご説明してきましたが、節約ばかりで疲れる。支出の見直しは普段から意識しているという方もいらっしゃるかと思います。
ですので、次は、収入について記載していきます。
4.1. 退職後も働く選択肢
近年では、シニア世代の労働市場も広がっており、退職後も無理のない範囲で働くことで収入を得ることが可能です。
例えば、以下のような働き方があります。
• シルバー人材センターでの仕事
• パート・アルバイト(スーパー、コンビニ、事務作業など)
• 在宅ワーク(ライティング、データ入力など)
特に在宅ワークは体力的な負担が少なく、インターネット環境があれば可能なため、人気があります。
4.2. 年金の繰り下げ受給
公的年金は繰り下げ受給(65歳以降に受給開始)を選択すると、1か月遅らせるごとに0.7%増額されます。
例えば、70歳まで繰り下げると最大42%増額されるため、長生きするほど有利になります。
ただし、繰り下げる間の生活費をどうするか考える必要があります。
4.3他人資本の活用による資産形成
資産運用についてのお話について話しが前後するかもしれませんが、もう1点楽しい老後を送るために必要とされていることがあります。
先程は、NISA・iDeCo、について、説明してきましたが、今度は、他人資本を活用した資産形成について説明していきます。
他人資本の活用についてですが、わかりやすく言うと、銀行等の金融機関から借り入れを起こして投資をするということです。
株や現物資産には、個人向けのフリーローンを除いて、金融機関が融資してくれるところはありませんが、唯一、不動産については、銀行は融資をしてくれます。
詳細については、よく学んでいただく必要があり、別途ご案内しますが、日本が、マネタリーベースを増加させたことにより、円の価格が下落を続け、物価が上昇を続けています。
不動産についても同じことが言えます。
下落を続ける円を借りてきて、上昇を続ける現物(不動産)に投資することで、資産形成のスピードを加速させることができます。
おまけに、借入ですので、元金が減っていく分も加味するとNISAやiDeCo等の積み立てや貯蓄型の保険に入るよりも資産形成のスピードが全く違います。
但し、繰り返しになりますが、不動産投資についてよく学んでいただく必要がありますので、よく勉強していただきたいと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。楽しい老後を暮らすためには、まず、早いうちからの資産形成が必要であることや毎月の収支の管理が必須となっていることがよくわかっていただけたかと思います。
今回記載した内容を正しく理解し、正しくすべて実践していただければ、必ず楽しい老後が送れるようになります。
もし、現役世代で、定年退職後から70代以降の生活に不安を感じず楽しい老後を暮らしていきたいとお考えの方であれば、一刻も早く行動に移してみてください。
今回記載した内容は全般的な内容になります。個別具体的な内容について知りたい、資産形成をしなければならないのは、わかったが、もう少し勉強したい、等疑問点やなかなか自分で動き出すことができない場合は、信頼できるお金の専門家であるファイナンシャルプランナーに是非お問合せください。
私のブログを拝見いただいた方々へ。是非私のLINEをフォローしてみてください。今なら無料特典プラス無料相談を行っております。是非LINEフォローしてみてください。